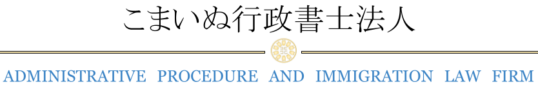福祉サービスが導入され、穏やかに過ごしていた宮田さん(仮名)。しかし冬に入り、外出する姿が見えなくなった。「大丈夫」としか言わない宮田さんに不安を抱えたまま、12月の支援が終わった。
あの日曜日の昼過ぎの電話を、私は一生忘れないだろう。
年が明けて一月も半ばになっていた。正月の間も宮田さんから特に連絡はなく、来週にはいつもどおり訪問する予定だった。携帯が鳴った。ケアマネージャーからだった。
「配食弁当が二日間、受け取られていないと業者から連絡がありました」
胸の奥が、すっと冷たくなった。
配食弁当の見守り機能が、最悪の形で作動したのだ。毎日届く弁当が取られていない。それは、玄関先に人が出てこないということを意味している。
その日の夕方、ケアマネージャーと一緒に宮田さんの自宅へ向かった。いつもと変わらない外観だった。古い木造住宅。外壁のペンキは相変わらず剥がれている。ただひとつ違ったのは、玄関のドアノブに配食弁当のビニール袋が二つ、ぶら下がっていたことだった。
チャイムを押した。反応はない。もう一度。何度も押した。声をかけた。返事はなかった。外階段から二階に上がってみた。窓の鍵が開いていた。恐る恐る窓を開けたが、宮田さんの姿は見えない。これ以上、私たちが中に入るわけにはいかない。警察と消防に通報した。
静かな住宅街に赤い光が点滅した。パトカー、救急車、消防車。近所の方々が驚いて出てきた。状況を説明し、警察官に中に入ってもらった。
しばらくして、警察官が戻ってきた。「二階で横になった状態で発見されました。すでに死後硬直が始まっています」
覚悟はしていた。していたつもりだった。でも実際にその言葉を聞いたとき、頭の中が真っ白になった。六十六歳だった。支援を始めてまだ二年。最低でもあと十年は続くと思っていた。
最後に、宮田さんの様子を写真で見せてもらった。苦しそうな表情はしていなかった。警察官が言った。「眼球も充血していないので、苦しまずに亡くなったのだと思います」——その言葉を聞いて、少しだけ救われた気持ちになった。
同時に、あの十二月の訪問が頭をよぎった。「大丈夫、大丈夫」。あのとき、もっと踏み込んで聞いていたら。もっと強く病院を勧めていたら。考えても答えは出ない。でも、考えずにはいられなかった。
一通りの手続きが終わったあと、近所の方々に宮田さんが亡くなったことを報告して回った。「えっ、宮田さんが……」。皆さん驚いていた。変わった人だったけれど、ゴミ出しの日を教えてあげたり、回覧板を届けてくれたり。小さな気遣いの積み重ねが、宮田さんの暮らしを支えていた。せめて、私たちから直接お伝えしたかった。
宮田さんが亡くなったあと、残された問題は大きかった。身寄りがない以上、ご遺体は最終的に市役所が対応することになる。火葬はされるだろう。しかし、納骨先はどうなるのか。宮田さんのお母さまは共同墓地に眠っている。せめて同じ場所に——そう思って翌月曜日、市役所の担当者に電話した。「お気持ちはわかりますが、残念ながらそれは難しいです」。行政の対応にはルールがある。頭ではわかっていた。受話器を置いたあと、しばらく動けなかった。
そしてもうひとつ、大きな問題があった。宮田さんの財産だ。実子はいない。兄弟姉妹もいない。両親もすでに他界している。推定相続人は不明のまま。持ち家と、数千万円の預金が残されていた。宙に浮いた財産は、空き家になった自宅とともに、しばらく動かないままだった。
私が何より後悔したのは、このことだった。宮田さんとの間に、死後事務委任契約を結んでいなかった。遺言も作成していなかった。
この契約さえあれば、宮田さんのお母さまと同じ墓地に納骨することも、遺品の整理も、私たちの手でやれたかもしれない。遺言があれば、宙に浮いた財産の行き先も決められた。疎遠な親族や国庫に渡るのではなく、宮田さん自身の意思で、お世話になった人や団体に託すこともできた。
存命中に、なぜもっと強くこの話を持ちかけなかったのか。宮田さんの理解力の問題があった。判断能力がどの程度あるのか不明瞭だったから、安易に契約に持ち込むわけにはいかなかった。でも、方法はあったかもしれない。時間をかけて丁寧に説明していれば。本人が理解できる形で伝えていれば。あのとき、もう一歩踏み込んでいれば——。
この後悔は、今も消えていない。宮田さんの支援は、こうして終わった。自宅は空き家になり、財産の行方は不透明なまま。お骨がお母さまのそばに行けたのかどうかも、私にはわからない。
あれから数年が経った。私は今、行政書士として終活に関わる仕事をしている。任意後見契約、死後事務委任契約、遺言書の作成。肩書きは変わったが、やっていることの根っこは変わらない。あの福祉の現場で学んだことが、今の仕事の土台になっている。宮田さんのような方を、もう出したくない。制度の狭間に落ちる前に、元気なうちに備えておくこと。「自分が死んだあと、誰に何を頼むか」を決めておく。それだけで、結末はまったく違ったものになる。あなたの周りに、宮田さんのような方はいないだろうか。あるいは、あなた自身が「まだ先のことだから」と思っていないだろうか。宮田さんは六十六歳だった。「そのとき」は、突然やってくる。