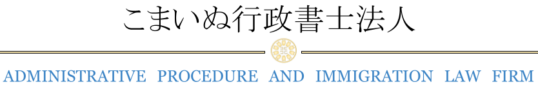母の死に気づかず一週間過ごしていた宮田さん(仮名・65歳)。後見制度が使えない中、私たちは法人との私文契約で月一回の見守り支援を始めた。
「ああ、来たの」
毎月の訪問日、宮田さんはいつもそう言って迎えてくれた。少し照れくさそうな顔で、でも嬉しそうでもあった。
支援が始まってからの宮田さんの暮らしは、穏やかだった。月に一回、私たちが自宅を訪ねて、一緒に銀行に行く。必要なお金をおろして、生活費の確認をする。特別なことは起きない。大きなトラブルもない。季節だけが静かに移り変わっていった。
宮田さんは、不思議な人だった。テレビが好きで、お笑い番組をよく見ていた。訪問するたびに「昨日のテレビ見た?」と聞いてくる。見ていないと言うと、少しがっかりした顔をして、それでも一生懸命その番組の面白さを説明してくれた。話し方にはどこか子どものような素直さがあって、近所の方々にもその人柄で可愛がられていたようだった。
そんな穏やかな日々に、転機が訪れたのは支援開始から一年ほど経った夏のことだった。訪問した職員が、宮田さんの体調がおかしいことに気づいた。顔色が悪い。聞けば、数日前から腹痛と下痢が続いているという。
病院嫌いの宮田さんだ。普段なら絶対に行かない。しかしこのときはさすがに辛かったのだろう。説得に応じて病院に行き、診察を受けた。結果は食中毒。薬を処方してもらい、幸い数日で回復した。
ただ、この一件は関係者全員に強い危機感を共有させた。もし発見がもっと遅れていたら。もし訪問のタイミングがずれていたら。月に一回の見守りだけでは、こういう事態に対応しきれない。
行政の担当者、地域包括支援センターの職員、そして私たち法人の担当者。みんなで集まって話し合い、宮田さんに福祉サービスの導入を提案することにした。
「別にいいよ、大丈夫だから」
最初は、やっぱり断られた。宮田さんにとって、他人が自分の生活に入ってくることへの抵抗感は根強いものがあった。でも食中毒の経験がよほど堪えたのだろう。何度かの説得を経て、ようやくしぶしぶ了承してくれた。
導入したのは二つ。一日一回の配食弁当サービスと、週三回の訪問看護サービスだ。
配食弁当には見守り機能がついている。毎日決まった時間に届けられる弁当を受け取ったかどうかで、安否を確認できる仕組みだ。宮田さんの場合、一人暮らしで近しい身内もいない。毎日誰かが玄関先に来るというだけで、大きな安全網になる。
ただ、宮田さんの反応は正直だった。「これ、あんまり美味しくないな」——初日からぶつぶつ言っていた。味付けが薄い、量が少ない、と毎回のように文句を言う。でも、残さず食べてはいた。文句を言える元気があるうちは大丈夫だろう、と私たちは笑っていた。
一方、訪問看護サービスのほうは意外にもすんなり受け入れた。看護師が週三回、自宅を訪問して健康状態をチェックする。血圧を測ったり、体調の変化を聞いたりする。宮田さんは人と話すことが好きだったのかもしれない。看護師の訪問を嫌がる様子はなく、むしろ世間話を楽しんでいるようだった。
サービスが始まって数ヶ月、宮田さんは少しずつ新しい暮らしに馴染んでいった。配食弁当の味にも慣れてきたのか、文句の回数が減った。看護師とも顔なじみになり、冗談を言い合う関係になっていた。支援者としては、ほっとする時期だった。
次はもう一歩踏み込んだ支援を検討する段階だと判断した。台所の掃除や簡単な調理のサポート。ホームヘルパーサービスの導入を、関係者会議で提案した。部屋の中は相変わらず散らかっていたし、自炊している様子もあまりなかった。客観的に見れば必要な支援だった。
しかし、宮田さんの答えは明確だった。「自分でやれるから、いいよ」。何度提案しても同じ答えだった。玄関先で弁当を受け取るのと、家の中で一緒に過ごすのとでは、宮田さんにとっての「距離感」がまったく違うのだろう。
「本人の意思の尊重」と「客観的に必要な支援」の間で、私たちは何度も揺れる。正解はない。そのときにできる最善を選ぶしかない。
そうしているうちに、季節は冬に変わった。十二月の訪問日。いつもどおり宮田さんの自宅を訪ねた。「ああ、来たの」——迎えてくれる言葉はいつもと同じだった。でも、なにかが少し違った。
食中毒を起こして以来、宮田さんが自分でコンビニに買い物に行っている様子がなかった。以前はときどき出かけていたのに、最近はまったく見かけないと近所の方も言っていた。「ご飯、ちゃんと食べてますか」と聞いてみた。「大丈夫、大丈夫」——宮田さんは、それしか言わなかった。
配食弁当は毎日届いている。最低限の栄養はそれでとれているだろう。でも、一日一食の弁当だけで冬を越せるのか。それ以上踏み込んで聞くべきだったのかもしれない。でも、あのときの私は「大丈夫」というその言葉を、信じることにした。
それが、宮田さんに会った最後の日になるとは思わなかった。