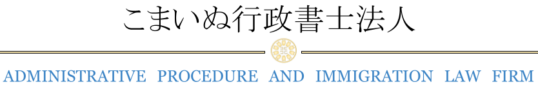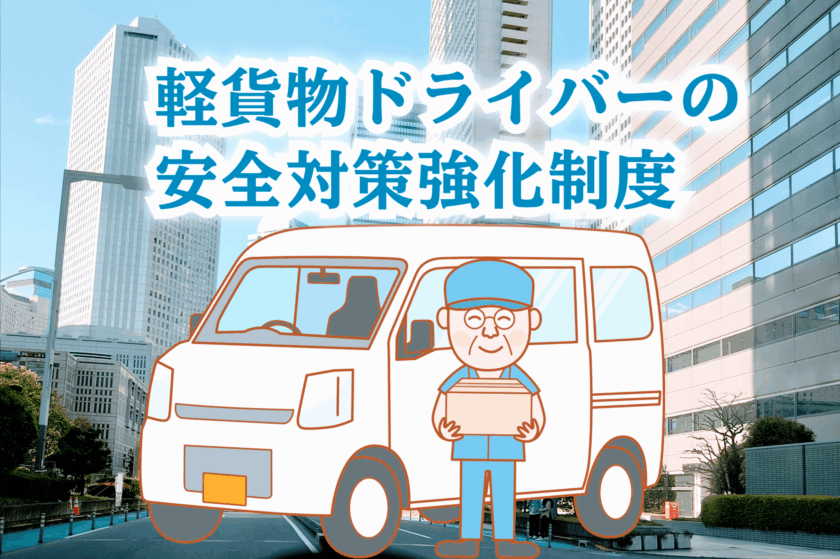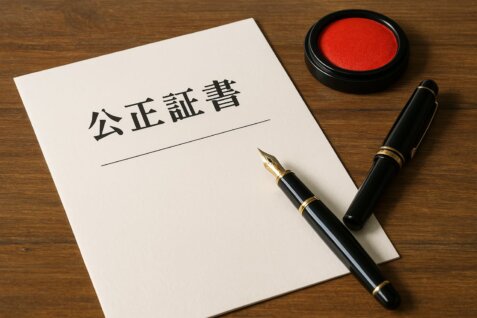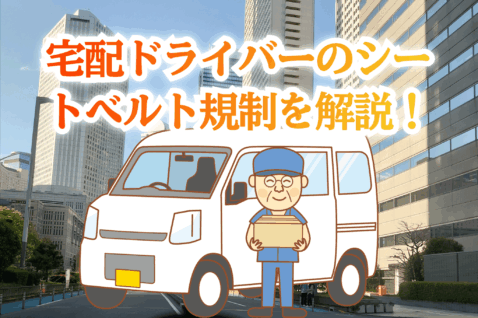法改正で変わる軽貨物運送業!2025年4月からの安全対策強化制度を解説
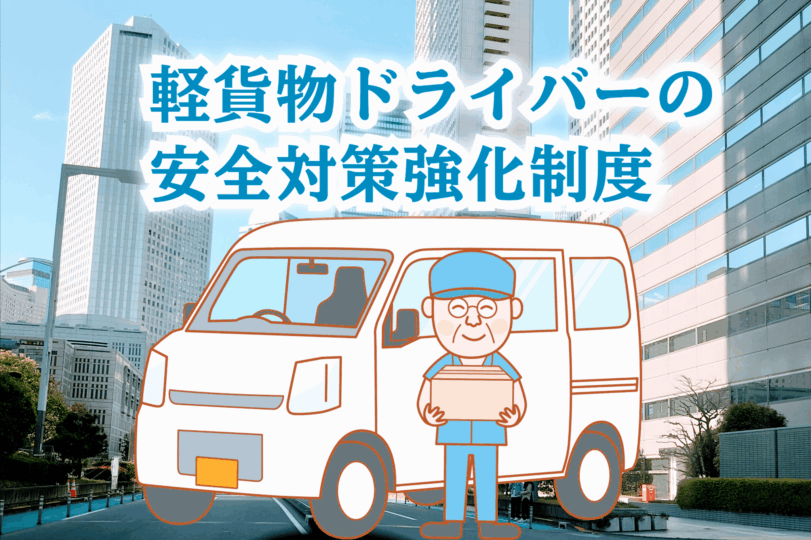
2025年4月から、貨物軽自動車運送事業(いわゆる軽貨物・黒ナンバー)に対する安全対策が大幅に強化されます。これは宅配需要の増加に伴い軽自動車による配送が拡大する一方で、事故件数も増加していることを背景としています。この記事では、新制度の概要から事業者がすべき対応、安全管理者の役割まで、分かりやすく解説します。個人事業主から法人まで、すべての軽貨物事業者に関わる重要な制度変更ですので、ぜひご確認ください。
📝新制度の概要と対象者
2025年(令和7年)4月1日から施行される新制度は、軽貨物事業者の安全対策を強化するもので、主に以下の対策が含まれています。
主な安全対策
- 貨物軽自動車安全管理者の選任・届出の義務化
- 初任運転者等への特別な指導・適性診断の実施
- 業務記録の作成・保存(1年間)
- 事故記録の作成・保存(3年間)
- 重大事故発生時の国土交通大臣への報告
- 点呼の実施と記録
- 運転者の勤務時間の遵守
制度の対象者
この制度の対象となるのは、「四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者」です。つまり、軽トラックやバンなどの軽自動車で荷物の配送を行う事業者が対象です。なお、バイク便事業者は今回の安全管理者選任義務の対象外となります。
また、個人で事業を行っている方でも、一人親方や個人事業主であれば対象になります。個人タクシーと似たような感覚で考えると分かりやすいでしょう。「自分は一人だから関係ない」とお考えの方も、事業として軽自動車で荷物を運んでいるなら対象となりますので注意が必要です。
📝事業形態別の対応方法
個人事業主(一人事業主)の場合
個人事業主の方は、基本的に自分自身を安全管理者として選任することになります。配偶者や家族従業者を選任することも認められていますが、その場合は必要な講習を受講させる必要があります。
具体的な対応として以下の手順が必要です:
- 貨物軽自動車安全管理者講習を受講する(自分自身が安全管理者になる場合)
- 管轄の運輸支局に安全管理者選任の届出を行う
- 業務記録(運行記録)の作成と保存体制を整える
- 点呼の実施と記録の体制を整える
【実務上のポイント】
個人事業主の方は、朝の出発前と帰着後の点呼を自分自身で行うことになります。スマートフォンアプリを活用して点呼記録を残すと便利です。また、アルコールチェックもスマホに接続できる小型のアルコールチェッカー(3,000円程度から市販されています)を使うと良いでしょう。
法人の場合
法人の場合は、営業所ごとに1名以上の安全管理者を選任し、届出を行う必要があります。複数の営業所がある場合は、それぞれの営業所ごとに選任する必要があります。
具体的な対応として以下の手順が必要です:
- 安全管理者として選任する社員に貨物軽自動車安全管理者講習を受講させる
- 管轄の運輸支局に安全管理者選任の届出を行う
- 運転者に対する指導・監督体制を構築する
- 運転者に対する点呼体制を構築する
- 業務記録、事故記録等の作成・保存体制を整える
【実務上のポイント】
法人の場合、特に複数のドライバーを抱える場合は、クラウド型の運行管理システムの導入が効率的です。点呼記録や業務記録を自動で管理できるシステムを活用することで、管理の手間を大幅に削減できます。費用は月額3,000円〜10,000円程度のものが多く、事業規模に応じて選択するとよいでしょう。
📝開業時期別の対応スケジュール
既存事業者(2025年3月31日以前に届出済みの方)
すでに事業届出を行っている既存事業者の方には、猶予期間が設けられています。2027年(令和9年)3月31日までに安全管理者の選任と届出を行う必要があります。ただし、それ以外の安全対策(業務記録の作成・保存、点呼の実施など)は2025年4月1日から必要です。
【対応スケジュール例】
- 2025年4月〜:業務記録の作成・保存、点呼の実施と記録開始
- 2025年4月〜2026年9月:安全管理者講習の受講(余裕をもって)
- 2026年10月〜2027年3月:安全管理者選任の届出(期限内に)
新規開業事業者(2025年4月1日以降に届出する方)
2025年4月1日以降に事業届出を行う新規事業者の方は、事業開始と同時に安全管理者の選任や業務記録の作成などすべての安全対策を実施する必要があります。
【対応スケジュール例】
- 事業開始前:安全管理者講習の受講
- 事業届出時:安全管理者選任の届出も同時に行う
- 事業開始日:業務記録の作成・保存、点呼の実施と記録開始
【実務上のポイント】
新規開業の方は、事業計画を立てる段階から安全対策の実施を織り込んでおくことが重要です。特に安全管理者講習は予約が混み合うことが予想されるため、開業準備と並行して早めに受講予約をしておくことをお勧めします。
📝必要な記録と保存義務
新制度では、以下の記録の作成と保存が義務付けられています。
業務記録(1年間保存)
以下の項目について記録を作成し、1年間保存する必要があります:
- 運転者等の氏名
- 車両番号(ナンバープレート)
- 業務の開始・終了の日時と地点
- 業務に従事した距離
- 主な経過地点
事故記録(3年間保存)
事故が発生した場合は、以下の項目について記録を作成し、3年間保存する必要があります:
- 乗務員等の氏名
- 事故の発生日時
- 事故の発生場所
- 事故の概要
- 事故の原因
- 再発防止対策
点呼記録
運行前後の点呼を実施し、以下の項目を記録する必要があります:
- 点呼実施者名
- 運転者名
- 点呼日時
- 点呼方法(対面、電話等)
- 酒気帯びの有無
- 運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況
- 日常点検の実施状況
- 指示事項
- その他必要な事項
【帳簿の様式について】
国土交通省が公表している様式例を利用することが推奨されますが、必要な項目がすべて含まれていれば独自の様式を使用することも可能です。電子データでの保存も認められていますので、クラウド型管理システムやエクセル等のソフトウェアを活用するとよいでしょう。
【実務上のポイント】
一人で運行される個人事業主の方は、スマホのメモアプリなどを活用して簡易的に記録する方法もあります。ただし保存期間内はデータが消えないよう定期的なバックアップをお忘れなく。国交省のサイトからダウンロードできるエクセル様式を活用するのも良い方法です。
📝貨物軽自動車安全管理者とは
「貨物軽自動車安全管理者」とは、軽貨物事業における安全の確保のために選任が義務付けられた管理者です。トラック運送業の「運行管理者」に相当する役割を担います。
安全管理者の主な業務
- 運転者に対する指導・監督
- 点呼の実施
- 運転者の勤務時間の管理
- 業務記録・事故記録の作成・管理
- 事故防止対策の実施
- 健康管理・労務管理の支援
安全管理者の選任基準
安全管理者として選任できるのは、以下のいずれかの要件を満たす方です:
- 貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前2年以内に修了した者
- 貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ、貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日前2年以内に修了した者
- 当該事業者が一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業も経営している場合に、その運行管理者として選任されている者
一人事業主・兼務の場合
個人事業主の場合は、基本的に自分自身が安全管理者となります。この場合も、必要な講習を受講する必要があります。自分自身が管理者であると同時に運転者でもあるという二重の立場になりますが、点呼などは自分自身で行い記録することになります。
法人の場合で役員や社員が安全管理者を兼務する場合も、実務上は本来の業務と安全管理業務を並行して行うことになります。重要なのは、安全管理業務を確実に実施し、その記録を残すことです。
【実務上のポイント】
一人事業主の方が自分で点呼を実施する場合、スマホアプリで「本日の体調:良好」「アルコールチェック:異常なし」などと記録するだけでも大丈夫です。アルコールチェッカーの写真を撮っておくと、より確実な証拠になります。大切なのは継続して実施することです。
📝講習の受講について
安全管理者として選任されるためには、所定の講習を受講する必要があります。講習には以下の2種類があります。
貨物軽自動車安全管理者講習
安全管理者に選任される前に受講が必要な講習です。講習時間は5時間以上で、内容は以下のとおりです:
- 自動車運送事業、道路交通等に関する法令
- 運行管理の業務に関すること
- 自動車事故防止に関すること
- 修了試問及び補習
貨物軽自動車安全管理者定期講習
選任後2年ごとに受講が必要な講習です。講習時間は2時間以上です。
講習の受講方法
講習は国土交通省が登録した講習機関で受講する必要があります。現在、独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)などが講習機関として登録されています。今後も登録機関は増えていく見込みです。
講習はeラーニング(オンライン)形式で受講できる場合もあります。お住まいの地域や業務の都合に合わせて、適切な受講方法を選択しましょう。
【実務上のポイント】
講習はeラーニングで受講できる場合が多いので、業務の合間に自分のペースで受講できます。ただし、本人確認のための顔認証機能等があるので、代理受講はできません。修了証明書は大切に保管し、コピーを取っておくと安心です。講習費用は概ね10,000円前後ですが、機関によって異なります。
📝講習事業者になるための要件
貨物軽自動車安全管理者講習を実施する講習機関になるには、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。以下はその主な要件です。
主な登録要件
- 適切な講師の確保(18歳以上で運行管理者資格者証を所持し、1年以上の実務経験または所定の研修修了が必要)
- 適切な教材・カリキュラムの整備
- 講習事務規程の整備
- 帳簿・記録の管理体制の整備
- eラーニング方式の場合は、本人確認機能や不正防止機能などを備えたシステム整備
申請手続き
講習機関として登録を受けるには、所定の申請書と添付書類を国土交通大臣に提出します。主な添付書類には、講師の資格を証明する書類、教材、講習事務規程などがあります。
国土交通省のウェブサイトから申請書のサンプルや自己チェックシートなどをダウンロードできます。これらを参考に申請準備を進めるとよいでしょう。
まとめ
2025年4月からの新制度は、軽貨物事業者にとって大きな変化をもたらします。業界全体の安全性向上を目的としたこの制度変更に、早めに対応することが重要です。個人事業主の方も対象となりますので、講習の受講や記録の作成など、必要な準備を計画的に進めましょう。
当法人では、軽貨物事業者の皆様の安全対策強化に関するサポートも行っております。書類の準備や届出手続きでお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。