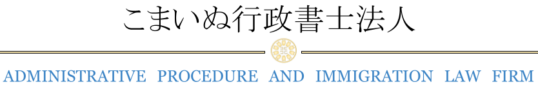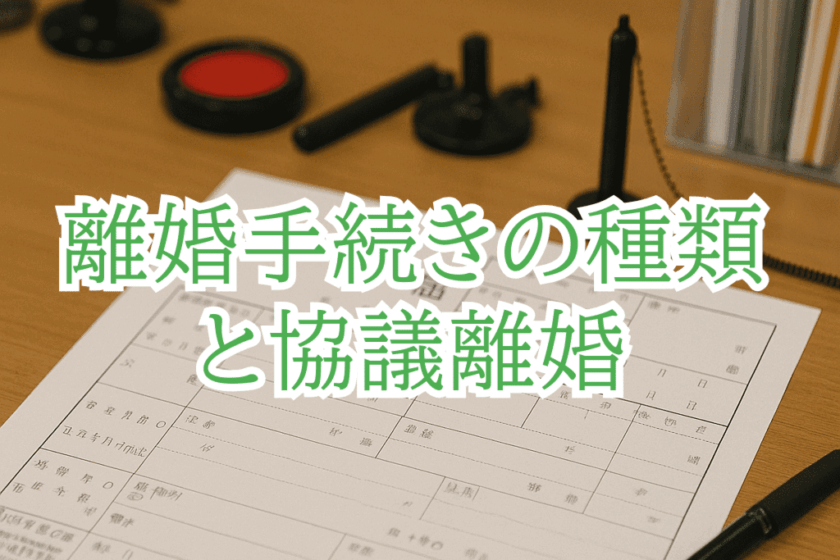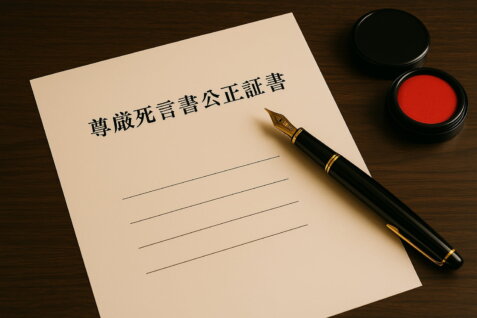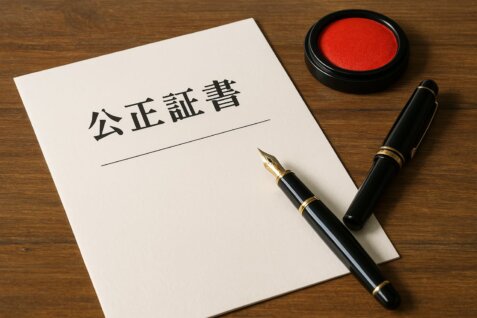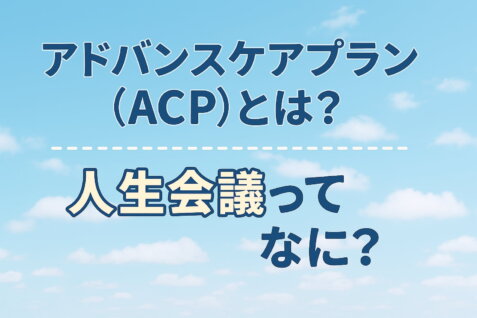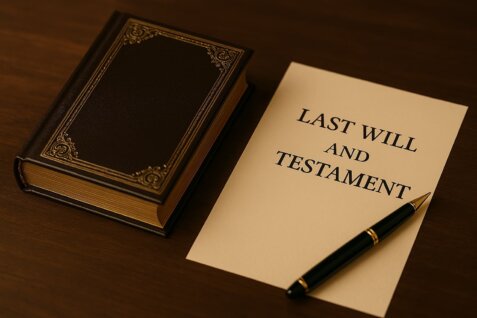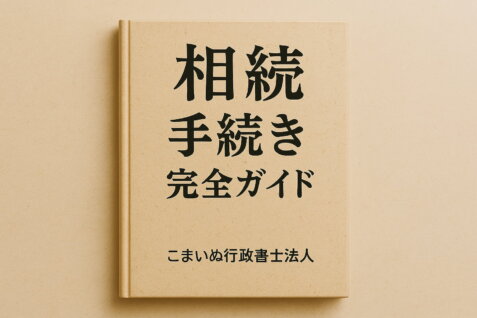公正証書にもできるの?協議離婚制度とそのメリット・デメリットを行政書士が詳しく解説
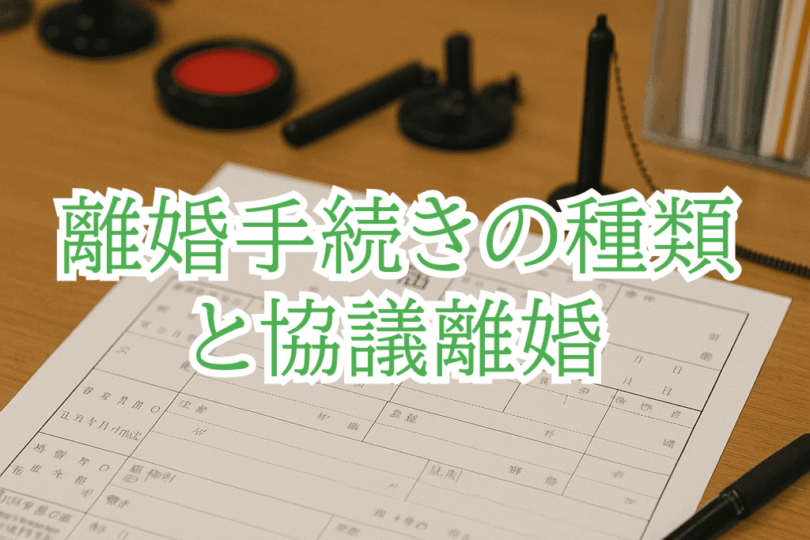
「離婚を考えているけれど、どんな手続きが必要なのだろう」「協議離婚という言葉は聞いたことがあるけれど、本当に話し合いだけで離婚できるの?」そんな不安や疑問をお持ちではないでしょうか。
実は、日本での離婚の約87%は協議離婚という方法で行われています。これは夫婦の話し合いによって成立する離婚方法ですが、適切な手続きを踏まなければ、後々トラブルになることも少なくありません。本記事では、離婚の種類と特徴、特に協議離婚の進め方や注意点について、行政書士の視点から詳しく解説します。あなたの新しい人生のスタートを、より確実なものにするためにお役立てください。
目次
📝日本の離婚制度の全体像
日本における離婚方法は、大きく分けて4つあります。それぞれに特徴があり、夫婦の状況に応じて選択することになります。
4つの離婚方法
- 協議離婚:夫婦の話し合いのみで成立する離婚(民法第763条)
- 調停離婚:家庭裁判所の調停委員を介して話し合う離婚(家事事件手続法第244条、第268条)
- 審判離婚:調停不成立後、裁判所の審判により成立する離婚(家事事件手続法第284条)
- 裁判離婚:離婚訴訟を提起し、判決により成立する離婚(民法第770条)
最新の離婚統計データ
厚生労働省の「令和4年(2022)人口動態統計」によると、日本の離婚件数は約17万9,099件で、離婚率(人口千対)は1.47となっています。これは前年比で若干の減少傾向にあります。
離婚方法の内訳を見ると、協議離婚が約87%と圧倒的多数を占めており、調停離婚が約8%、和解離婚が約3%、その他(審判離婚・判決離婚)が約2%となっています。このデータから、日本では話し合いによる解決が主流であることがわかります。
また、同居期間別では5年未満での離婚が最も多く全体の約31%を占めています。一方で、同居期間20年以上のいわゆる「熟年離婚」も約21%と増加傾向にあり、離婚の時期が二極化していることが特徴的です。
📝協議離婚とは?基本を理解する
協議離婚は、日本の離婚制度の基本となる方法です。民法第763条に「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる」と規定されているように、夫婦間の合意のみで成立します。
協議離婚の特徴
- 離婚理由を問わない:法定離婚原因(不貞行為、悪意の遺棄など)がなくても、双方の合意があれば離婚できます
- 裁判所の関与がない:調停や裁判と異なり、第三者の介入なしに当事者だけで決められます
- 手続きが簡便:離婚届に必要事項を記入し、役所に提出するだけで成立します
- 費用が安い:基本的に離婚届の提出は無料で、弁護士費用なども必須ではありません
協議離婚が向いているケース
以下のような状況では、協議離婚が適しています。
- 夫婦間で冷静な話し合いができる関係にある
- 離婚条件について大きな対立がない
- 共有財産が少ない、または分割方法が明確
- 子どもがいない、または親権について合意している
- お互いに新しい人生を前向きに歩もうとしている
ただし、DVや経済的な格差が大きい場合、一方的に不利な条件を押し付けられる危険性があるため、専門家への相談や調停の利用を検討することが重要です。
📝協議離婚で決めるべき重要事項
協議離婚では、離婚後の生活に関わる重要事項について、夫婦で話し合って決める必要があります。口約束だけでなく、書面に残すことがトラブル防止の鍵となります。
1. 子どもに関する事項
親権者の決定は、未成年の子どもがいる場合は必須です。離婚届に親権者を記載しないと受理されません。親権は「身上監護権」と「財産管理権」から構成され、通常は一方の親が両方の権利を持ちます。
養育費については、金額、支払期間、支払方法を具体的に決めます。裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」(令和元年版)を参考にすることが一般的です。例えば、支払義務者の年収が500万円、権利者の年収が200万円、14歳以下の子ども1人の場合、月額4~6万円が目安となります。
面会交流は、子どもの健全な成長のために重要です。頻度(月○回)、時間、場所、方法(宿泊の可否など)を具体的に定めます。子どもの意思や年齢も考慮する必要があります。
2. 財産に関する事項
財産分与は、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産を分配することです。対象となる財産には、預貯金、不動産、有価証券、保険、退職金(婚姻期間に対応する部分)などが含まれます。原則として2分の1ずつ分けますが、個別の事情により調整することも可能です。
慰謝料は、離婚原因を作った配偶者が支払う損害賠償です。不貞行為、DVなどが原因の場合に発生することが多く、金額は50万円~300万円程度が相場ですが、個別の事情により異なります。
年金分割は、婚姻期間中の厚生年金記録を分割する制度です。合意分割と3号分割があり、離婚後2年以内に手続きする必要があります。
3. その他の重要事項
- 住居の問題:持ち家の場合、どちらが住み続けるか、売却するか、住宅ローンの負担をどうするか
- 連帯保証の解消:配偶者の借金の連帯保証人になっている場合の対処方法
- 生命保険の受取人変更:受取人を配偶者にしている場合の変更手続き
📝協議離婚のメリット・デメリット
協議離婚を選択する前に、そのメリットとデメリットを正しく理解しておくことが大切です。
協議離婚のメリット
- 手続きが迅速:合意さえできれば、最短1日で離婚が成立します。調停や裁判のように数ヶ月~数年かかることはありません
- 費用が最小限:離婚届の提出は無料です。公正証書を作成する場合でも数万円程度で済みます
- プライバシーが守られる:裁判所での手続きと異なり、離婚理由などの詳細が公になることはありません
- 柔軟な取り決めが可能:法律の枠にとらわれず、夫婦の事情に応じた独自の取り決めができます
- 精神的負担が少ない:第三者を介さないため、対立が深刻化しにくく、比較的穏やかに進められます
協議離婚のデメリット
- 力関係の不均衡:経済力や交渉力に差がある場合、弱い立場の側が不利な条件を受け入れざるを得ないことがあります
- 取り決めの不履行リスク:口約束や私的な書面だけでは、養育費などの支払いが滞った際の強制力がありません
- 法的知識の不足による不利益:専門家の助言なしに進めると、本来受け取れるはずの権利を見落とす可能性があります
- 感情的な対立の激化:直接交渉するため、感情的になりやすく、話し合いが決裂することもあります
- 財産の把握が困難:相手の財産を十分に把握できず、適正な財産分与ができない場合があります
これらのデメリットを回避するためには、専門家(弁護士・行政書士など)のサポートを受けながら進めることをおすすめします。特に、公正証書の作成は、将来のトラブル防止に大きな効果があります。
📝協議離婚の手続きの流れ
協議離婚の手続きは比較的シンプルですが、適切な順序で進めることが重要です。以下、具体的な流れを説明します。
ステップ1:離婚意思の確認と話し合い
まず、お互いに離婚の意思があることを確認します。その上で、前述の重要事項(親権、養育費、財産分与など)について話し合います。感情的にならず、冷静に話し合うことが大切です。必要に応じて、第三者(カウンセラーや専門家)の同席も検討しましょう。
ステップ2:離婚条件の合意と書面化
話し合いで合意した内容を「離婚協議書」として書面にまとめましょう。後のトラブルを防ぐため、できるだけ詳細に記載することが重要です。可能であれば、この段階で公正証書の作成を検討することをお勧めします。
ステップ3:離婚届の準備
離婚届は市区町村役場で入手できます。また、多くの自治体でホームページからダウンロードも可能です。記入にあたっては以下の点に注意してください。
- 夫婦双方の署名(令和3年9月1日から戸籍法の一部改正により、戸籍の届書への押印義務は廃止され、届出人の署名のみで足りることになりました。)
- 成年者2名の証人の署名・押印
- 親権者の指定(未成年の子がいる場合)
- 離婚後の氏(旧姓に戻るか、婚姻時の氏を継続するか)
ステップ4:離婚届の提出
記入済みの離婚届を市区町村役場に提出します。提出は夫婦のどちらか一方でも可能ですが、以下の書類を持参してください。
- 離婚届
- 戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑(訂正が必要な場合に備えて)
ステップ5:離婚後の手続き
離婚届が受理されたら、以下の手続きを速やかに行います。
- 住民票の異動:転居する場合は14日以内に手続き
- 氏の変更手続き:旧姓に戻る場合の各種名義変更
- 健康保険の変更:扶養から外れる場合は国民健康保険への加入など
- 年金の変更届:第3号被保険者は変更が必要
- 児童手当・児童扶養手当の申請:ひとり親になる場合
📝離婚協議書と公正証書の重要性
協議離婚では、合意内容を書面に残すことが極めて重要です。特に、公正証書として作成することで、将来のトラブルを大幅に減らすことができます。
離婚協議書とは
離婚協議書は、離婚時の合意内容を記載した私文書です。法的な形式は決まっていませんが、以下の項目を含めることが一般的です。
- 離婚の合意
- 親権者の指定
- 養育費の金額・支払方法・期間
- 面会交流の方法・頻度
- 財産分与の詳細
- 慰謝料の有無と金額
- 年金分割の合意
- 清算条項(他に債権債務がないことの確認)
公正証書にするメリット
離婚協議書を公正証書にすることには、以下の大きなメリットがあります。
1. 強制執行認諾文言による強制力
養育費や慰謝料の支払いが滞った場合、「強制執行認諾文言」が付された公正証書があれば、裁判を経ることなく、直ちに給与差押えなどの強制執行が可能です。これは私文書の離婚協議書にはない、公正証書最大のメリットです。
2. 高い証明力
公証人が作成する公文書であるため、後から「そんな約束はしていない」「署名を強要された」などと争われるリスクが極めて低くなります。
3. 原本の保管
公正証書の原本は公証役場で原則として20年間保管されるため、紛失の心配がありません。
公正証書作成の手順
- 事前準備:離婚協議書の内容を固め、必要書類(戸籍謄本、印鑑証明書など)を準備
- 公証役場への相談:最寄りの公証役場に連絡し、作成日時を予約
- 公証人との打ち合わせ:内容の確認と修正
- 作成当日:原則として夫婦双方が出席し、内容を確認後、署名押印
- 費用:目的価格により異なるが、通常3~5万円程度
📝別居中の生活費(婚姻費用)について
離婚を検討する中で別居を選択する夫婦も多くいます。この場合、別居中であっても夫婦には「婚姻費用分担義務」があることを知っておく必要があります。
婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。民法第760条は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定めており、別居中でも収入の多い配偶者は、収入の少ない配偶者に対して生活費を支払う義務があります。
婚姻費用の内容
婚姻費用には以下のようなものが含まれます。
- 衣食住に関する費用
- 医療費
- 子どもの教育費・養育費
- 交際費など社会生活上必要な費用
婚姻費用の算定方法
婚姻費用の金額は、まず当事者間の話し合いで決めますが、合意できない場合は家庭裁判所の調停・審判で決定されます。裁判所では「婚姻費用算定表」(令和元年版)を参考に金額を決定します。
例えば、夫(会社員)の年収が600万円、妻(パート)の年収が100万円、15歳未満の子ども2人を妻が養育している場合、婚姻費用の目安は月額12~14万円程度となります。
婚姻費用請求の注意点
- 請求時期:原則として請求した時点から認められるため、別居後は速やかに請求することが重要
- 支払期間:別居開始から離婚成立または同居再開まで
- 別居の正当性:一方的な別居や不貞行為による別居の場合、減額される可能性がある
- 協議離婚との関係:婚姻費用の支払いを受けながら、離婚協議を進めることも可能
別居期間が長期化すると経済的負担も大きくなるため、早期の解決を目指すことが双方にとって重要です。
📝財産分与の期限と注意点
離婚時に財産分与について十分に話し合えなかった場合でも、離婚後に請求することは可能です。ただし、重要な期限があることを知っておく必要があります。
財産分与請求権の除斥期間
民法第768条第2項ただし書きは、「離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない」と定めています。これは「除斥期間」と呼ばれ、離婚成立日から2年を経過すると、財産分与を請求する権利が消滅することを意味します。
この2年という期間は、時効とは異なり中断や停止がありません。つまり、どのような事情があっても、2年を過ぎれば原則として財産分与請求はできなくなります。
除斥期間の例外
ただし、以下のような場合は例外的に2年経過後も請求が認められる可能性があります。
- 財産隠しが発覚した場合:離婚時に相手が故意に財産を隠していたことが後から判明した場合
- 詐欺・強迫による場合:財産分与の合意が詐欺や強迫によるものだった場合
- 当事者間の新たな合意:2年経過後でも双方が合意すれば財産の移転は可能(ただし税務上は贈与として扱われる可能性あり)
期限内に行うべきこと
2年の除斥期間内に財産分与について解決するため、以下の対応を検討しましょう。
- 協議による解決:まずは元配偶者と話し合い、合意書を作成
- 調停の申立て:協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てる
- 内容証明郵便での請求:とりあえず請求の意思表示を明確にしておく
財産分与と税金
財産分与には税金の問題も関わってきます。
- 不動産や株式の場合:時価が取得価格を上回る場合、譲渡所得税が課税される可能性
- 居住用財産の特例:マイホームの場合、3,000万円特別控除などの特例が適用される場合あり
- 贈与税の問題:過大な財産分与は贈与とみなされる可能性
財産分与は複雑な問題を含むため、期限に余裕をもって専門家に相談することをおすすめします。当法人でも協議離婚書作成にあたって財産分与に関するご相談を承っております。
まとめ
日本の離婚の約87%を占める協議離婚は、夫婦の話し合いだけで成立する最もシンプルな離婚方法です。手続きが簡単で費用も安く、プライバシーも守られるというメリットがある一方で、合意内容の履行確保や法的知識の不足による不利益といったリスクもあります。
協議離婚を成功させるポイントは、①感情的にならず冷静に話し合うこと、②重要事項について漏れなく取り決めること、③合意内容を公正証書などの書面に残すこと、④必要に応じて専門家のサポートを受けることです。特に、養育費や財産分与など金銭が関わる事項については、公正証書の作成を強くおすすめします。
また、財産分与請求権の2年という除斥期間や、別居中の婚姻費用など、知らないと不利益を被る可能性のある制度もあります。離婚は人生の大きな転機です。新しい人生を前向きにスタートするためにも、適切な手続きと準備が重要です。
こまいぬ行政書士法人では、紛争性がない場合に限って、離婚協議書の作成支援や公正証書作成のサポートの際には、財産分与や養育費に関するご相談も含めて、協議離婚に関する様々なお手伝いをしております。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。あなたの新しい一歩を、法律の専門家として全力でサポートいたします。