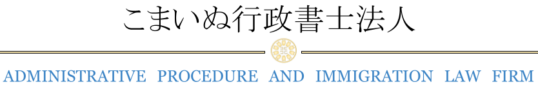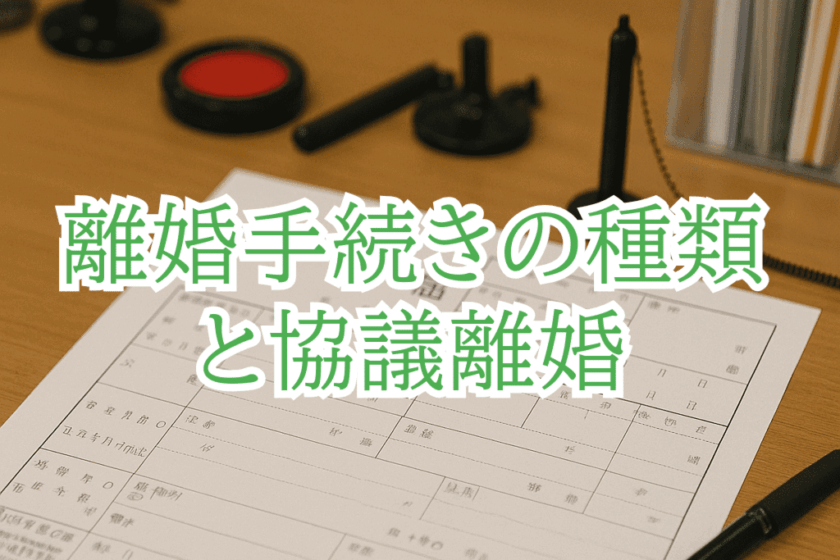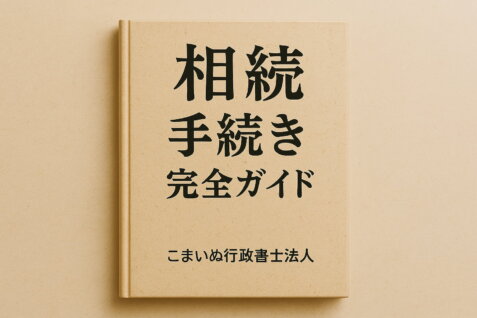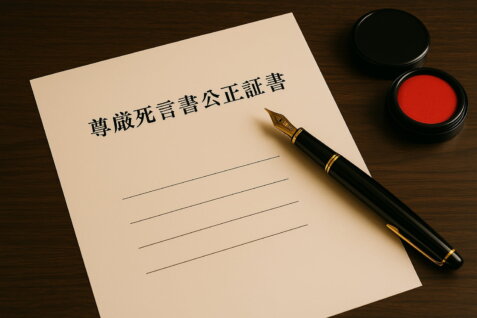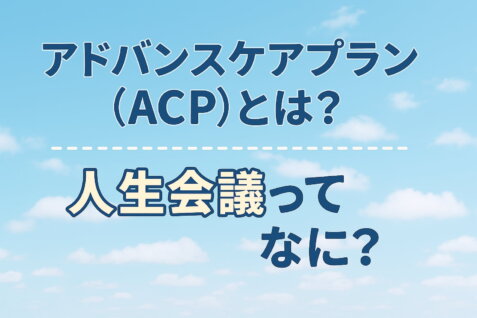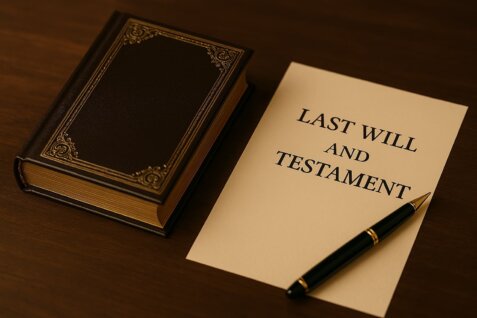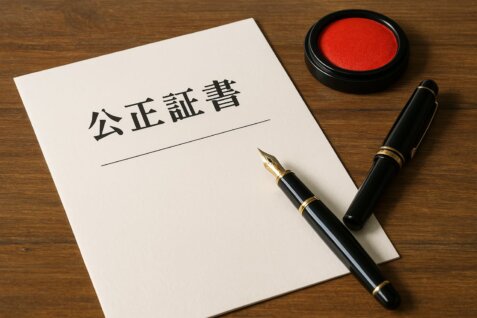離婚手続きの種類と協議離婚:離婚制度を行政書士が解説
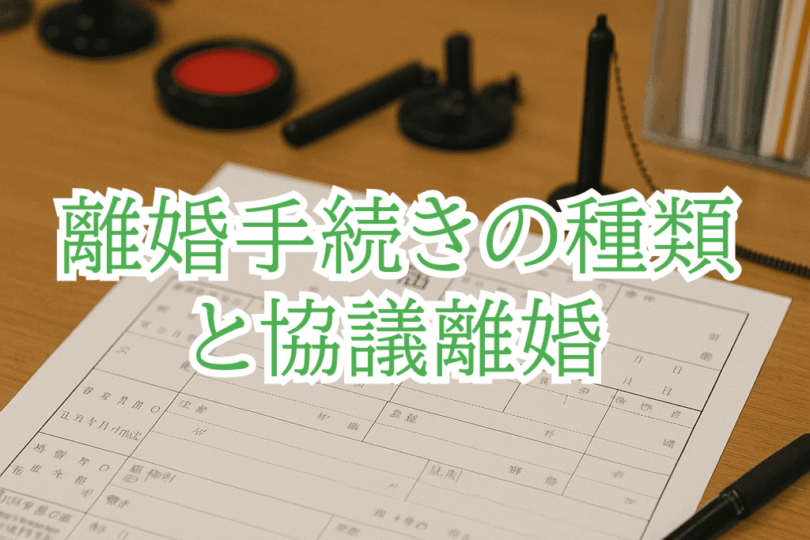
離婚を考えるとき、どのような手続きがあるのか、自分にはどの方法が適しているのか迷われる方も多いのではないでしょうか。日本では離婚方法にいくつかの種類があり、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあります。本記事では、最も一般的な「協議離婚」を中心に、離婚の種類や手続きの流れ、注意点について詳しく解説します。また、日本における最新の離婚統計データや婚姻費用の算定方法、財産分与の期限についても触れていますので、適切な離婚方法を選ぶ際の参考にしていただければ幸いです。
目次
📝離婚の種類と最新統計
日本における離婚方法は主に4つに分類されます。これらの方法は手続きの複雑さや期間、費用などが異なるため、状況に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。
離婚の4つの方法
- 協議離婚:夫婦の話し合いのみで合意し、離婚届を提出する方法(民法第763条)
- 調停離婚:家庭裁判所の調停委員を介して話し合いを行う方法(民法第766条)
- 審判離婚:調停が不成立の場合に家庭裁判所の審判で決定される方法(民法第770条)
- 裁判離婚:調停不成立後に訴訟を起こして判決で離婚する方法(民法第770条)
離婚方法の割合(最新統計)
令和5年の厚生労働省の統計データによると、日本における離婚方法の割合は以下のようになっています。
| 離婚方法 | 割合 |
|---|---|
| 協議離婚 | 約87% |
| 調停離婚 | 約7.5% |
| 審判離婚 | 約2% |
| 裁判離婚(和解含む) | 約2.5% |
このデータから明らかなように、日本では圧倒的多数の夫婦が協議離婚を選択しています。
日本の離婚統計データ
厚生労働省の「人口動態統計」によると、2023年の日本の離婚件数は約18万3,814件で、人口1,000人あたりの離婚率は1.5となっています。世界的に見ると、日本の離婚率は比較的低い水準にあります。総務省統計局の「世界の統計2024」では、ジョージアの3.8、モルドバやベラルーシの3.7と比較すると、日本の離婚率は低いことがわかります。
また、年齢層別では、30代の離婚率が最も高く、同居期間別では、5年未満の離婚が最も多い傾向にあります。一方で、同居期間20年以上の「熟年離婚」の件数も増加しており、1985年の約2万件から2020年には約3万9千件とほぼ倍増しています。
📝各離婚方法の進行過程と期間
離婚方法によって進行過程や期間は大きく異なります。それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。
協議離婚の進行過程と期間
協議離婚は最もシンプルな離婚方法で、夫婦間の話し合いだけで進めることができます。
- 手続きの流れ:夫婦で離婚条件について話し合い → 合意形成 → 離婚協議書の作成(任意) → 離婚届の提出
- 必要期間:早ければ1日で完了することも可能ですが、条件面での話し合いに時間がかかることが多く、平均的には数週間〜数ヶ月程度
- 費用:基本的には離婚届の提出費用のみ(無料)。ただし、離婚協議書や公正証書を作成する場合は別途費用が発生
調停離婚の進行過程と期間
夫婦間の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用することになります。
- 手続きの流れ:調停申立て → 調停期日の設定 → 複数回の調停期日で話し合い → 調停成立 → 調停調書の作成 → 離婚届の提出
- 必要期間:平均3〜6ヶ月程度(調停の回数や争点により変動)
- 費用:調停申立費用1,200円 + 郵便切手代(数千円程度)
審判離婚・裁判離婚の進行過程と期間
調停が不成立となった場合は、審判または裁判による離婚手続きへと進みます。
- 審判離婚の期間:通常1〜3ヶ月程度(調停から継続して行われる)
- 裁判離婚の期間:平均1〜2年程度(事案の複雑さによりさらに長期化することも)
- 費用:裁判の場合、収入印紙代(訴額により変動)+ 弁護士費用(30〜50万円以上)が必要
このように、協議離婚が最も短期間かつ低コストで離婚手続きを進められることがわかります。しかし、条件面で合意形成が難しい場合は、第三者を介した調停などの手続きが必要となります。
📝協議離婚の詳細解説
日本の離婚の約87%を占める協議離婚について、より詳しく解説します。
協議離婚の定義と特徴
協議離婚とは、夫婦が話し合いによって離婚することに合意し、離婚届に双方が署名・押印して役所に提出することで成立する離婚方法です。裁判所を介さず、当事者間の合意のみで成立するため、手続きがシンプルで費用も低く抑えられるという特徴があります。
民法第763条では「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる」と規定されており、日本の離婚制度の基本となっています。協議離婚では離婚理由を証明する必要がなく、双方が合意すれば理由を問わずに離婚できます。
協議離婚に必要な手続きと書類
協議離婚を成立させるために必要な手続きと書類は以下の通りです。
- 離婚届:市区町村の役所で入手可能。夫婦両方の署名・押印と成年者2名の証人の署名・押印が必要
- 夫婦それぞれの印鑑:認印でも可能(ただし実印が望ましい)
- 本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証など
- 戸籍謄本:本籍地以外の役所に提出する場合に必要
協議離婚で決めるべき重要事項
協議離婚では、離婚後の生活に関わる以下の重要事項について話し合いで決める必要があります。
- 子どもの親権:未成年の子どもがいる場合、どちらが親権者になるか決定(離婚届に記載必須)
- 養育費:子どもの養育に必要な費用の分担方法と金額
- 面会交流:非親権者と子どもとの交流方法や頻度
- 財産分与:婚姻中に築いた財産の分配方法
- 慰謝料:離婚の原因を作った配偶者に対する賠償金
- 年金分割:婚姻期間中の厚生年金の分割方法
これらの事項について合意がまとまらない場合は、協議離婚が成立せず、調停離婚などの他の方法を検討する必要があります。
📝協議離婚のメリット・デメリット
協議離婚には様々なメリットとデメリットがあります。自分の状況に適しているかどうか判断する際の参考にしてください。
協議離婚のメリット
- 手続きが簡単:裁判所を介さず、夫婦の合意と離婚届の提出だけで完了するため手続きが簡単
- 費用が安い:基本的に離婚届の提出だけなので費用がほとんどかからない
- 期間が短い:合意さえできれば、すぐに離婚が成立する
- プライバシーが守られる:裁判所などの公的機関を通さないため、離婚理由などのプライベートな情報が外部に漏れにくい
- 当事者の自由意思を尊重:双方の話し合いで条件を決められるため、それぞれの事情に合った柔軟な取り決めが可能
協議離婚のデメリット
- 合意形成が難しい場合がある:双方の主張が対立すると、話し合いがまとまらず長期化することも
- 専門的なアドバイスを受けられない:裁判所などの第三者が関与しないため、不公平な合意をしてしまうリスクがある
- 取り決めが守られない可能性:法的強制力のある公正証書等を作成しないと、約束が守られなくても強制執行が難しい
- 財産分与後の名義変更手続きが複雑:財産分与で不動産などを取得した場合、調停調書や判決文と違い、名義変更の手続きが複雑になることがある
財産分与後の名義変更における注意点
協議離婚で財産分与として不動産を取得した場合、名義変更手続きには特に注意が必要です。調停離婚や裁判離婚の場合は調停調書や判決文に基づいて名義変更が可能ですが、協議離婚の場合は以下のような問題が生じることがあります。
- 元配偶者の協力が必要:不動産の名義変更(登記)は、公正証書があっても基本的に共同申請が必要です。元配偶者の協力が得られないと手続きが進まない場合があります
- 住宅ローンの名義変更:不動産にローンが残っている場合、金融機関の承諾を得て債務者変更の手続きが必要
- 手続きの複雑さ:名義変更には多くの書類や手続きが必要で、専門知識がないと困難
- 期限の問題:財産分与の請求権には離婚成立後2年間という除斥期間があり、その期間を過ぎると権利が消滅する可能性がある
これらの問題を回避するためには、離婚協議書や財産分与契約書を公正証書で作成しておくことが重要です。また、専門家(弁護士・司法書士など)に相談しながら手続きを進めることをお勧めします。
📝協議離婚に向いているケース
協議離婚は全ての夫婦に適しているわけではありません。以下のようなケースでは、協議離婚が特に有効です。
コミュニケーションができる夫婦
離婚について冷静に話し合いができる関係性であれば、協議離婚が最適です。感情的な対立が少なく、双方が合理的な判断ができる場合、スムーズに合意形成が可能です。たとえ離婚理由に不倫などがあっても、話し合いで解決できる関係性であれば協議離婚が向いています。
財産が少ない、または明確な夫婦
共有財産が少ない、またはすでに分け方が明確な場合は、協議離婚が適しています。複雑な財産関係がない場合、分割方法の話し合いもスムーズに進みやすいでしょう。
子どもがいない、または親権で揉めない夫婦
子どもがいない場合や、親権について両者の意見が一致している場合は、協議離婚が向いています。親権問題は離婚時の最も大きな争点となることが多いため、この点で合意ができていれば協議離婚がスムーズに進行します。
熟年離婚のケース
子育てが終わり、それぞれが新たな人生を模索する熟年期の夫婦の場合、協議離婚が選ばれることが多いです。厚生労働省の統計によれば、同居期間20年以上の離婚(いわゆる熟年離婚)は年々増加傾向にあり、2020年には全離婚件数の約21.5%を占めています。
熟年離婚の主な特徴として以下が挙げられます:
- 子どもの独立:子どもが成人して独立していることが多く、親権問題が発生しない
- 年金分割の重要性:退職金や年金などの分割が重要な争点となる
- 住居の問題:長年住んできた家をどうするかという問題が生じやすい
- 新たな人生の模索:退職後の第二の人生をそれぞれの価値観で過ごしたいという願望
熟年離婚では特に、年金分割や退職金の分与、不動産の処理などについて専門家のアドバイスを受けながら進めることが重要です。また、離婚後の生活設計についても十分に検討しておく必要があります。
📝別居と婚姻費用について
離婚を検討する過程で別居するケースは少なくありません。別居中には、経済的に弱い立場の配偶者を保護するための「婚姻費用」という制度があります。
婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を送るために必要な一切の費用のことで、別居中も支払い義務があります。これは民法第760条に「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定されています。
婚姻費用の算定方法
婚姻費用の金額は、当事者間の話し合いで自由に決めることができますが、合意が難しい場合は、家庭裁判所の調停や審判で決定されます。その際、裁判所は「婚姻費用算定表」を参考にします。
令和元年12月23日に、裁判所から最新の婚姻費用算定表が公表されました。この算定表は、夫婦それぞれの年収と、子どもの有無・年齢によって、月額の婚姻費用が算出できるようになっています。
例えば、夫の年収が400万円、妻の年収が200万円、子どもが2人(15歳以上1人、14歳以下1人)の場合、妻が受け取れる婚姻費用の目安は月額8〜10万円程度となります。詳細な金額は、裁判所のウェブサイトで公開されている最新の算定表で確認できます。
別居期間と財産分与の関係
長期間の別居が財産分与にどう影響するかは、重要な検討ポイントです。基本的に、財産分与の対象となる共有財産は「夫婦で協力して築いた財産」ですが、別居後は実質的に協力関係が薄れるため、別居後に取得した財産は原則として共有財産とは認められない傾向があります。
ただし、協議離婚の場合は、夫婦の合意で柔軟に決めることができます。話し合いで、別居後の財産も含めて分与の対象とすることも可能です。重要なのは、何を共有財産と考え、どのように分けるかについてしっかりと話し合い、書面に残しておくことです。
📝財産分与に関する制限と注意点
離婚時の財産分与には、特に注意すべき時間的制限があります。離婚時に取り決めできない場合でも、離婚後に財産分与を請求することは可能ですが、期限を過ぎると権利が消滅してしまう可能性があります。
財産分与請求権の除斥期間
財産分与を請求できる期限は、民法第768条第2項但書に「離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない」と規定されています。この2年という期間は「除斥期間」と呼ばれ、時効とは異なり中断や延長が認められません。
この2年の期間は、離婚届が受理された日から起算されます。期間内に当事者間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てることで、2年の除斥期間経過後も財産分与を受けられる可能性があります。
財産分与の時効に関する注意点
財産分与の内容について合意が成立した後、実際に金銭の支払いや財産の引き渡しを受ける権利については、通常の債権と同様に時効の適用があります。
- 協議で決めた場合:権利を行使できると知った時から5年間(民法第166条第1項第1号)
- 調停・審判・判決で決めた場合:10年間(民法第169条第1項)
なお、2024年5月に「民法等の一部を改正する法律」が可決され、2026年までに財産分与の請求期限が2年から5年に延長される予定です。これにより、より適切な権利行使の機会が確保されることが期待されています。
財産分与の特殊事例
特殊なケースとして、以下のような場合には、2年の除斥期間経過後でも財産分与が認められる可能性があります。
- 財産の隠匿があった場合:一方が財産を隠していたことが後から発覚した場合
- 詐欺や強迫による財産分与契約の無効:離婚時の財産分与の合意が詐欺や強迫によるものであった場合
- 当事者間の合意がある場合:2年経過後でも双方が合意すれば可能(ただし、税法上は贈与とみなされる可能性あり)
財産分与に関する権利を確実に守るためには、離婚前または離婚後すぐに専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。当法人でも財産分与に関するご相談に対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。
📝離婚協議書と公正証書の重要性
協議離婚をする際には、離婚条件を書面にまとめて残しておくことが非常に重要です。特に公正証書の作成は、離婚後のトラブル防止に効果的です。
離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚条件(財産分与、慰謝料、養育費、親権、面会交流など)について合意した内容を書面にまとめたものです。法的には私文書となり、当事者間で作成します。
離婚協議書には法的な様式は定められていませんが、一般的には以下の内容が含まれます。
- 離婚することの合意
- 親権者の決定(子どもがいる場合)
- 養育費の支払い方法と金額
- 面会交流の頻度と方法
- 財産分与の内容
- 慰謝料の有無と金額
- 年金分割の有無と割合
公正証書のメリット
離婚協議書を公正証書として作成することには、以下のような重要なメリットがあります。
- 高い証明力:公証人が作成する公文書なので、内容の真正性が法的に推定される
- 強制執行認諾文言の付与:養育費や慰謝料の支払いが滞った場合、裁判を経ずに強制執行できる
- 原本の永久保存:公証役場で原本が保管され、紛失のリスクがない
- 専門家のチェック:公証人が法的に問題のない内容であるかチェックする
- 心理的効果:当事者に契約内容を守る意識を高める効果がある
特に「強制執行認諾文言」を付けることができる点は、公正証書の最大のメリットです。これにより、養育費などの支払いが滞った場合に、改めて裁判を起こすことなく、直ちに差し押さえなどの強制執行手続きが可能になります。
公正証書作成のタイミング
公正証書は、離婚届を提出する前に作成することをお勧めします。離婚成立後は、相手が公正証書作成に協力してくれない可能性があるためです。ただし、すでに離婚が成立している場合でも、元配偶者の協力が得られれば公正証書を作成することは可能です。
公正証書の作成には両当事者の出席が必要です。通常は公証役場に出向いて手続きを行いますが、事前に公証役場に相談すれば、代理人を立てることも可能な場合があります。
協議離婚では、将来のトラブルを防ぐために、専門家(弁護士・行政書士など)のサポートを受けながら公正証書を作成することをおすすめします。当法人でも離婚公正証書の作成支援を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
日本の離婚方法のうち、約87%を占める協議離婚は、当事者間の話し合いだけで成立するシンプルな離婚方法です。費用が安く、期間も短いというメリットがある一方で、合意形成が難しいケースや、取り決めが守られないリスクもあります。
離婚を円滑に進めるためには、①お互いの信頼関係を保ちながら冷静に話し合うこと、②合意内容を公正証書などの書面にしっかりと残すこと、③必要に応じて専門家(弁護士・行政書士など)のサポートを受けることが重要です。また、財産分与請求権の2年という除斥期間や、別居中の婚姻費用の問題など、法律上の制限や権利についても正確に理解しておくことが大切です。
当法人では、協議離婚の手続きサポートや公正証書作成のアドバイス、財産分与に関する相談など、離婚に関する様々な法的サポートを提供しております。新しい人生のスタートを円滑に切るためにも、お気軽にご相談ください。