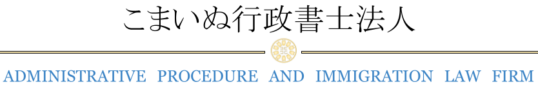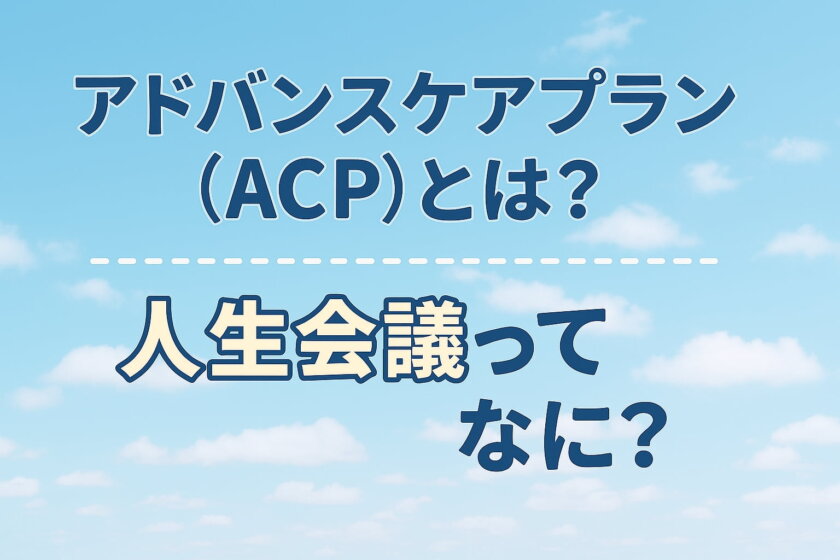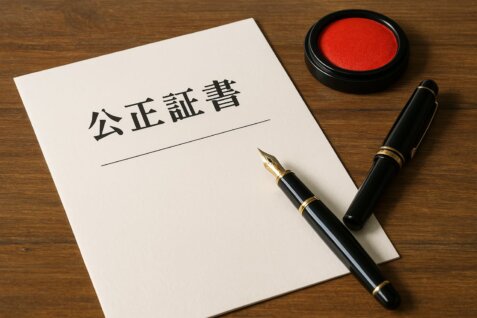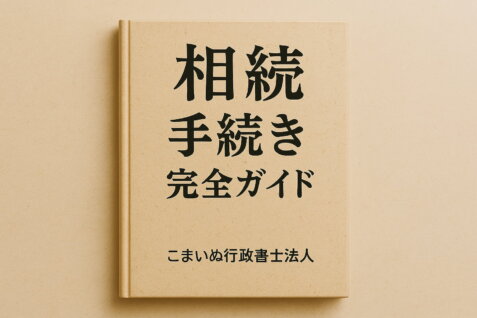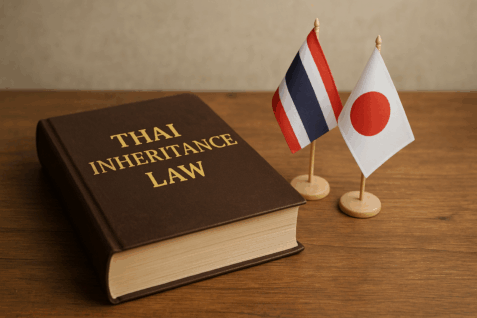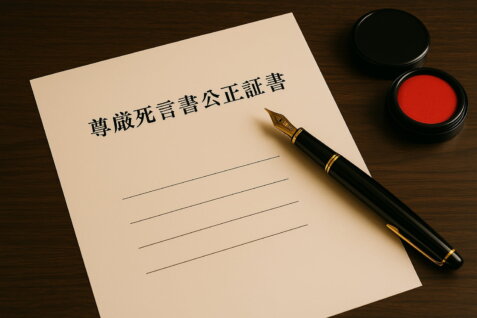アドバンスケアプランニング(人生会議)とは?行政書士が解説する将来の医療・ケアの準備
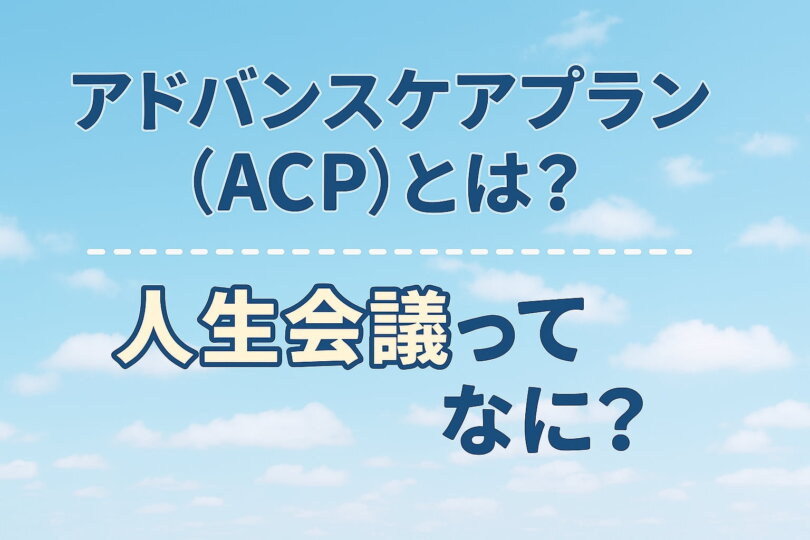
将来、自分で意思決定ができなくなったとき、どのような医療やケアを受けたいか考えたことはあるでしょうか?アドバンスケアプランニング(ACP)は、そうした将来に備えて自分の希望や価値観を前もって考え、家族や医療者と共有しておくプロセスです。日本では「人生会議」とも呼ばれ、厚生労働省も推進しています。この記事では、行政書士の視点から、アドバンスケアプランニングの概要や進め方、法的な側面について分かりやすく解説します。
📝アドバンスケアプランニング(人生会議)とは
アドバンスケアプランニング(ACP)とは、将来の意思決定能力が低下した際に備えて、自分の希望する医療やケアについて前もって考え、周囲の人と共有しておくプロセスのことです。日本では2018年より厚生労働省が「人生会議」という愛称を用いて普及啓発を行っています。
ACPは単なる書類作成ではなく、継続的な対話のプロセス自体をいいます。自分の価値観や人生の目標、どのような医療やケアを望むか(あるいは望まないか)について考え、家族や医療・ケア提供者、信頼できる人たちと共有していきます。これにより、将来自分で意思表示ができなくなった場合でも、自分の意向に沿った医療やケアを受けられる可能性が高まります。
「人生会議」という愛称について
厚生労働省は2018年に「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を改訂し、アドバンスケアプランニングの重要性を強調しました。同時に、より親しみやすく理解しやすい言葉として「人生会議」という愛称を提案しています。毎年11月30日は「いい看取り・看取られ」の日として、人生会議の日と定められています。
📝アドバンスケアプランニングの重要性
なぜアドバンスケアプランニングというプロセスが重要なのでしょうか。
- 自分の意思が尊重される可能性が高まる:自分の希望を前もって伝えておくことで、意思決定ができなくなった際でも、自分の価値観に沿った選択がなされやすくなる。
- 家族の精神的負担の軽減:突然の事態で家族が代理で決断を迫られる場合、「本人なら何を望むだろう」という葛藤が生じることがあり、事前に話し合っておくことで、そうした負担の軽減につながる。
- 医療・ケア提供者との意思疎通の円滑化:自分の希望を医療・ケア提供者と共有しておくことで、緊急時でもスムーズな対応が期待できる。
- 人生の最終段階をより自分らしく過ごせる:自分の価値観や希望に沿った医療やケアを受けることで、人生の最終段階をより自分らしく過ごすことができる。
超高齢社会を迎えた日本では、人生の最終段階における医療やケアの在り方が重要な課題となっています。高齢化に伴い認知症患者も増加する中、自分の意思を伝えられなくなる前に、自分の希望を周囲と共有しておくことの重要性はますます高まっています。
現場からの声
医療現場や介護施設からは「本人の意思が分からないまま、延命措置などの重要な決断を迫られることがある」「家族間で意見が分かれて対応に苦慮する」といった声が聞かれます。そうした状況を少しでも減らすために、元気なうちから考え、話し合っておくことが推奨されているのです。
📝アドバンスケアプランニングの具体的な内容と進め方
アドバンスケアプランニングでは、主に以下のような内容について考え、話し合います。
- 自分にとっての「良い人生」「良い最期」とはどのようなものか
- どのような医療やケアを望むか、あるいは望まないか
- 人生の最終段階をどこで過ごしたいか(自宅、病院、施設など)
- 延命治療に対する希望
- 自分に代わって意思決定をしてほしい人(代理意思決定者)は誰か
- 苦痛緩和についての希望
- 臓器提供や献体についての意向
進め方のステップ
アドバンスケアプランニングの進め方について絶対的な決まりはありません。人それぞれの考えや状況によって異なりますが、例えば以下のようなステップで進めるとよいでしょう。
- 自分自身で考える:まずは自分自身の価値観や希望について内省します。「何が自分にとって大切か」「どのような生き方、最期を迎えたいか」などを考えます。
- 信頼できる人と話し合う:家族や親しい友人、かかりつけ医などと話し合い、自分の希望を伝えます。また、定期的に話し合いの機会を持つことが理想的です。
- 文書化する:話し合った内容を文書にまとめておくと、後々の参考になります。ノートに書くだけでも良いですし、事前指示書(リビングウィル)や医療に関する希望を記した書類として作成しておくこともできます。
- 定期的に見直す:健康状態や価値観は時間と共に変化するので、定期的に内容を見直し、必要に応じて更新することが大切です。
- 必要に応じて専門家に相談する:法的な効力を持たせたい場合や、複雑な医療的判断が必要な場合は、法律専門家や医療の専門家などに相談することをおすすめします。
📝法的効力を持たせるための方法
アドバンスケアプランニングの結果を文書として残すだけでは必ずしも法的な拘束力はありませんが、以下のような方法を組み合わせることで、より法的効力を高めることができます。
- 任意後見契約:将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。医療行為に対する同意権を与えることはできませんが、日常的にかかわる機会が多いため、日頃から自分の意思を伝えておいていざというときに参考意見として医療現場に伝えてもらうことができるようになります。
- 医療に関する事前指示書(リビングウィル):延命治療や終末期医療に関する自分の希望を記した文書です。法的拘束力はありませんが、医療現場での参考にされます。
- 尊厳死宣言公正証書:公証人の面前で作成する公正証書形式の尊厳死宣言書です。現行の制度上完全な法的拘束力を持たせることまではできませんが、一定の公的な証明力があります。
上記で挙げたこれらの手段は単独で完璧なものではなく、それぞれに限界があります。そのため、複数の手段を組み合わせつつ、何より大切なのは家族や医療者との日頃からの対話です。
厚生労働省の「もしものときのために」
厚生労働省は「もしものときのために」という人生会議の提案書を公開しています。この様式に沿って自分の希望を記入し、家族や医療者と共有することも一つの方法です。ただし、この文書自体には法的拘束力はなく、あくまで参考資料として活用されます。
📝よくある疑問と回答
アドバンスケアプランニングについて、よくある疑問とその回答をまとめました。
| 疑問 | 回答 |
|---|---|
| いつ始めるべきか? | 特別な年齢制限はありません。成人であれば、健康なうちから始めることをお勧めします。特に高齢になってからや慢性疾患を抱えている場合は、より重要になります。 |
| 書いたら変更できない? | いいえ、いつでも変更可能です。実際、健康状態や考え方は変化することがあるため、定期的に見直し、必要に応じて更新することが推奨されています。 |
| 一人暮らしで身寄りがない場合は? | 身寄りがない方こそ、アドバンスケアプランニングが重要です。信頼できる友人や専門家(行政書士、社会福祉士、医療従事者など)との相談、法的書類の作成などを検討されるとよいでしょう。 |
| 医師は必ず従ってくれる? | 医療現場では実際上様々な制約があり、そのため現行制度ではどの方法をとったとしても必ずしも全ての希望が実現するとは限りません。ただし、明確に意思表示しておくことで、それが尊重される可能性は高まります。 |
| 費用はかかる? | 基本的な話し合いや「もしものときのために」の記入などには費用はかかりません。ただし、公正証書の作成や任意後見契約の締結などには費用が発生します。 |
これらの疑問に対する回答はあくまでも一般的なものです。個別の状況に応じた具体的なアドバイスが必要な場合は、医療従事者や社会福祉士などの各種専門家にご相談するのも手です。当法人でも、アドバンスケアプランニングに関連する法的サポートとして公正証書の作成支援サービスを提供しております。
まとめ
アドバンスケアプランニング(人生会議)は、将来の意思決定能力低下に備えて、自分の希望する医療やケアについて前もって考え、周囲と共有しておくプロセスです。単なる書類作成ではなく、継続的な対話を通じて、自分らしい人生の最終段階を迎えるための準備であり、家族の負担軽減にもつながります。
ご自身の意思をできるだけ効果的に明示するためには、任意後見契約や尊厳死宣言公正証書などの法的手段も検討することが有効です。ただし、何より大切なのは、家族や医療者との日頃からの対話です。「もしものとき」のことを考えるのは決して容易ではありませんが、それは自分自身と大切な人たちのための大切な準備といえます。
こまいぬ行政書士法人では、アドバンスケアプランニングに関連する法的書類の作成サポートや相談を承っております。お一人で悩まず、ぜひ専門家にご相談ください。