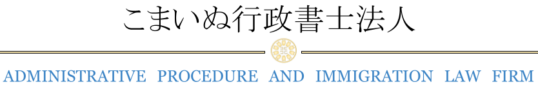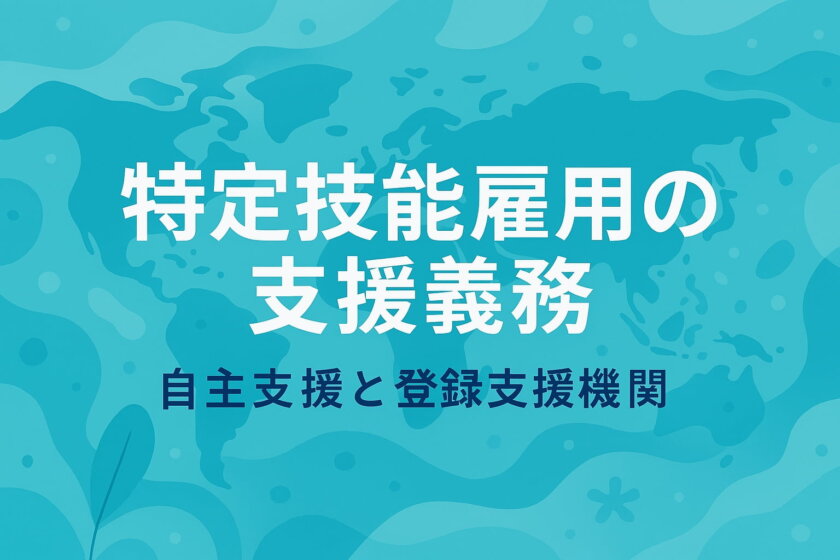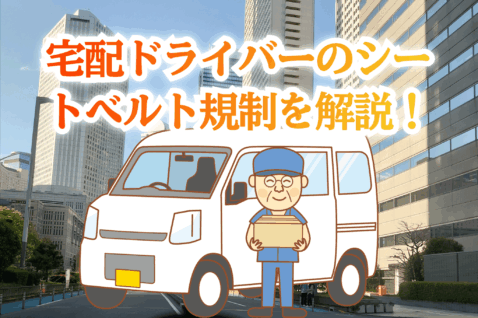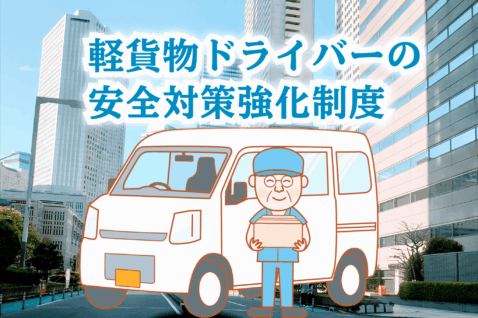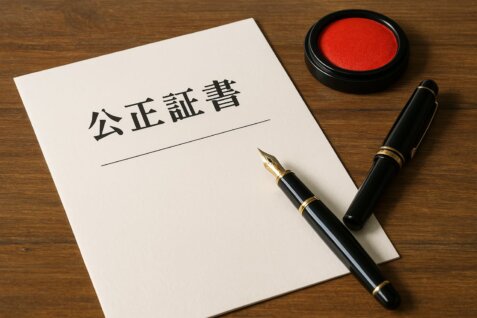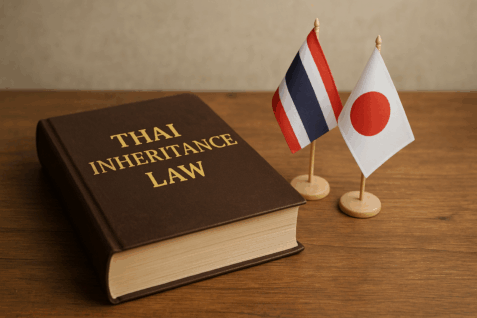特定技能制度と支援義務:自主支援か登録支援機関に委託か
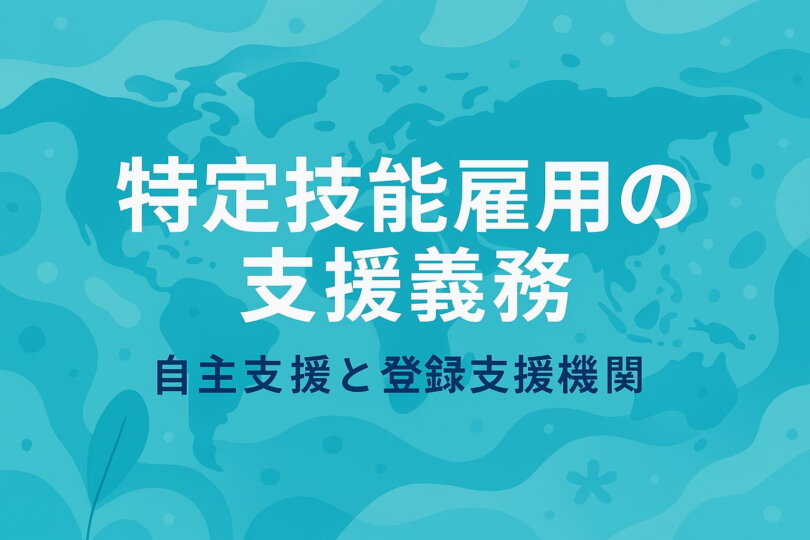
外国人材を雇用したいとお考えの事業者様にとって、「特定技能」という在留資格は魅力的な選択肢の一つです。しかし、特定技能外国人を雇用する際には、法律で定められた「支援」を行うことが必須となっています。この支援は自社で行う「自主支援」か、「登録支援機関」に委託するかの選択が必要です。本記事では、2025年最新の制度改正情報を踏まえ、なぜ支援が必要なのか、その内容とは何か、そして登録支援機関の役割や選び方について詳しく解説します。
目次
📝特定技能ビザとは:2025年最新情報
特定技能制度は、2019年4月に始まった制度で、日本国内で人材確保が困難な特定の産業分野における労働力不足に対応するために創設されました。当初は12の産業分野が対象でしたが、最新の制度改正により16分野に拡大されています。また、今後5年間の受け入れ目標数が大幅に増加し、34万5千人から82万人に引き上げられました。
特定技能ビザには「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。特に支援義務があるのは「特定技能1号」となります。特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、通算5年を上限として在留が認められます。
特定技能2号は、当初建設分野と造船・舶用工業分野のみが対象でしたが、2023年には介護を除く11分野に拡大され、熟練した外国人労働者が長期的に日本でキャリアを築く道が開かれています。
特定技能の対象産業分野(2025年現在)
2025年現在、特定技能の対象となる産業分野は16分野あり、各分野によって求められる技能試験や日本語能力の基準が異なります。
| 分野 | 特定技能1号 | 特定技能2号 | 主な業務内容 |
|---|---|---|---|
| 介護 | ◯ | × | 入浴、食事、排泄の介助、その他関連業務(2025年4月から訪問介護も解禁されました) |
| ビルクリーニング | ◯ | ◯ | 建築物内部の清掃 |
| 工業製品製造業 | ◯ | ◯ | 機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理、紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本 |
| 建設 | ◯ | ◯ | 土木、建築、ライフライン・設備 |
| 造船・舶用工業 | ◯ | ◯ | 造船、船用機械、舶用電気電子機器 |
| 自動車整備 | ◯ | ◯ | 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備 |
| 航空 | ◯ | ◯ | 空港グランドハンドリング、航空機整備 |
| 宿泊 | ◯ | ◯ | フロント、企画・広報、接客、レストランサービス |
| 農業 | ◯ | ◯ | 耕種農業全般、畜産農業全般 |
| 漁業・養殖業 | ◯ | ◯ | 漁業、養殖業全般 |
| 飲食料品製造業 | ◯ | ◯ | 飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、スーパーの惣菜製造を含む |
| 外食業 | ◯ | ◯ | 飲食物調理、接客、店舗管理 |
| 自動車運送業 | ◯ | ◯ | バス運転者、タクシー運転者、トラック運転者 |
| 鉄道 | ◯ | ◯ | 軌道整備、電気設備整備、車両整備、車両製造、運輸係員(運転士、車掌、駅係員) |
| 林業 | ◯ | ◯ | 育林、素材生産、林業種苗育成 |
| 木材産業 | ◯ | ◯ | 製材業、合板製造業などにおける木材の加工工程およびその附帯作業 |
新規追加分野と既存分野の変更点
2024年3月には、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野が新たに特定技能の対象となりました。また、既存の分野でも重要な変更がありました:
- 工業製品製造業:「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」から名称変更し、業務区分も大幅に拡大。紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本などが新たに追加されました。
- 造船・舶用工業:従来の6業務区分が造船、船用機械、舶用電気電子機器の3区分に再編され、各業務区分の作業範囲も拡大されました。
- 飲食料品製造業:食料品スーパーマーケットや総合スーパーマーケットの食料品部門における惣菜などの製造も対象となりました。
これらの変更は、日本の労働力不足が一層深刻化する中で、外国人材の活用範囲を拡大し、様々な産業分野のニーズに対応する狙いがあります。
📝特定技能における「支援」の義務とその理由
特定技能1号外国人を雇用する場合、受入れ企業(特定技能所属機関)は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、外国人が特定技能の活動を安定的かつ円滑に行えるように支援することが法律で義務付けられています。この支援義務は企業側にとって重要な責任となります。
なぜ支援が必要なのか?
「なぜ外国人を雇うだけでなく、支援までしなければならないのか」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。その理由は以下のとおりです:
- 言語・文化の壁:外国人が日本で生活・就労する際には、言語の壁や文化の違いが大きな障壁となります。日本人には当たり前のことも、外国人にとっては困難なことが多くあります。
- 社会保障や生活基盤の確立:住居の確保、各種公的手続き、医療機関へのアクセスなど、生活の基盤を整えるためのサポートが必要です。
- 外国人材の定着と能力発揮:適切な支援があれば、外国人材は早期に日本社会に適応し、その能力を十分に発揮できるようになります。
- 社会問題の防止:過去には外国人労働者が適切なサポートを受けられず、様々な社会問題が発生したケースがあった為、特定技能制度では、制度設計の段階でこうした問題を防止する仕組みとして支援義務が課されています。
特定技能制度では、外国人の受入れと同時に、受入れ企業による適切な支援を義務付けることで、外国人材が日本社会に溶け込み、安定して生活・就労できる環境を整えることを重視しています。
📝義務的支援と任意的支援の詳細
特定技能制度における支援は、「義務的支援」と「任意的支援」の2種類に分かれます。ここでは、それぞれの内容を詳しく解説します。
義務的支援(10項目)
義務的支援とは、特定技能外国人に対して必ず実施しなければならない支援のことです。以下の10項目が法令で定められています:
| 支援項目 | 具体的内容 | 実施時期・頻度 |
|---|---|---|
| 1. 事前ガイダンス | 雇用契約締結後、在留資格申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について説明 | 入国前(1回) |
| 2. 出入国する際の送迎 | 入国時・帰国時の空港と住居間の送迎 | 入国時・帰国時 |
| 3. 住居の確保・生活に必要な契約支援 | 賃貸借契約の締結支援、水道・電気・ガス等の契約支援 | 入国直後、住居変更時 |
| 4. 生活オリエンテーション | 日本の生活ルール、地域社会の習慣、交通機関の利用方法、災害時対応等について説明 | 入国後速やかに |
| 5. 公的手続等への同行 | 住民登録、社会保険・銀行口座開設等の手続きへの同行支援 | 入国後速やかに、必要に応じて |
| 6. 相談・苦情対応 | 外国人が理解できる言語での相談対応体制の整備 | 常時(24時間365日体制が理想的) |
| 7. 日本語学習の機会の提供 | 日本語学習教材の提供、日本語教室等の情報提供 | 継続的 |
| 8. 生活のための日本語習得の支援 | 日常生活で必要な日本語を習得するための支援 | 継続的 |
| 9. 定期的な面談・行政機関への通報 | 外国人本人と監督者との定期面談、問題があれば行政機関へ通報 | 3ヶ月に1回以上 |
| 10. 転職支援(会社都合による雇用終了時) | 会社都合で雇用契約が終了した場合の転職支援 | 雇用契約終了時(必要に応じて) |
これらの支援項目は、入国前から帰国時まで、外国人材の在留期間全体をカバーする内容となっています。また、多くの項目では「外国人が十分理解できる言語」での対応が求められており、多言語対応の必要性も高くなっています。
義務的支援の実施方法と注意点(2025年更新情報)
義務的支援を実施する際の主な注意点は以下のとおりです:
- 多言語対応:特に「事前ガイダンス」「生活オリエンテーション」「相談・苦情対応」「定期面談」などは、外国人が十分理解できる言語(原則として母国語)で行う必要があります。
- 記録の保存:支援の実施状況を記録し、保存しておくことが重要です。定期届出の際にも支援実施状況の報告が必要となります。
- 定期面談のオンライン対応(2025年新規情報):一定の条件の下で、オンラインでの実施が可能になりました。条件には、面談対象者の同意、面談の録画と一定期間の保管、年1回以上の対面面談(初回面談は対面)が含まれます。
- 送迎に関する変更(2025年新規情報):登録支援機関が受け入れ機関から委託を受けて送迎を行う場合、一定の条件下で登録支援機関の車両を利用することが認められるようになりました。
任意的支援
任意的支援とは、義務ではありませんが、外国人材の生活をより充実させ、日本社会への適応を促進するための支援です。法令上の義務ではありませんが、外国人材の定着率向上や能力発揮のためには重要な役割を果たします。
主な任意的支援の例としては、以下のようなものがあります:
- 日本語能力向上のための追加支援:日本語教室の費用負担、社内日本語勉強会の開催など
- 資格取得支援:キャリアアップのための資格取得支援や学習時間の確保
- 文化交流・地域貢献活動:地域の祭りやイベントへの参加支援、文化交流会の開催など
- 生活支援の充実:病院同行通訳、買い物支援、各種手続きのサポートなど
- レクリエーション活動:社内イベント、スポーツ大会、旅行などの企画
- 家族呼び寄せ支援:家族の呼び寄せを希望する場合の手続き支援
これらの任意的支援は、外国人材の満足度や定着率に大きく影響します。特に、同じ条件で複数の就職先を選べる状況では、こうした支援の充実度が外国人材の就職先選択の重要な基準となることがあります。
📝支援方法の選択肢:自主支援と登録支援機関
特定技能外国人への支援方法には、大きく分けて2つの選択肢があります。
自主支援(自社で行う場合)
自主支援とは、受入れ企業が自社で支援業務を行うことを指します。この場合、企業は支援責任者と支援担当者を選任し、外国人が理解できる言語で支援を提供できる体制を整える必要があります。
自主支援の体制整備には、以下の要件が必要です:
- 外国人が必要な支援を適切に受けられる支援体制があること
- 支援責任者(常勤で日本人)および支援担当者(常勤)が選任されていること
- 支援担当者が外国人と意思疎通できる能力を有すること
登録支援機関への委託
登録支援機関とは、出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関で、受入れ企業からの委託を受けて特定技能外国人への支援を行います。登録支援機関に支援計画の全部を委託した場合、受入れ企業は支援体制に関する基準を満たしたものとみなされます。
2025年5月時点で登録支援機関の数は1万件を超えており、その役割の重要性が増しています。これは、特に外国人労働者の受け入れ経験が少ない企業にとって、円滑な受け入れとサポート体制の構築に不可欠な存在となっています。
登録支援機関が満たすべき要件(登録支援機関事業者向け項目です)
登録支援機関として登録を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります:
- 過去5年以内に出入国・労働法令違反がないこと
- 5年以内に登録支援機関としての登録を取り消されていないこと
- 外国人が十分理解できる言語で支援できる体制があること
- 適切な支援計画を作成できる能力を有すること
- 支援責任者(常勤で日本人)・支援担当者(常勤)を選任していること
- 各種届出が適正に行われる体制が整備されていること
登録支援機関は、支援の実施状況について3ヶ月に1回以上の頻度で出入国在留管理庁に報告する義務があります(2025年4月以降は年1回に変更予定)。報告を怠ったり、支援が不適切だったりした場合は、登録の取消処分を受ける可能性があります。
📝自主支援と登録支援機関の違い
自主支援と登録支援機関への委託には、それぞれメリット・デメリットがあります。選択の際の参考として、主な違いを比較してみましょう。
自主支援のメリットとデメリット
- メリット:支援費用が抑えられる(登録支援機関への委託費が不要)
- メリット:外国人材と直接的なコミュニケーションが取れる
- メリット:会社の方針や文化に沿った支援が行える
- デメリット:専門知識(入管法や労働法)の習得が必要
- デメリット:外国語対応できる担当者の確保が必要
- デメリット:支援業務の負担が大きい(特に多数の外国人を雇用する場合)
- デメリット:定期届出などの事務作業が必要
登録支援機関委託のメリットとデメリット
- メリット:専門知識を持つ機関に任せられる安心感
- メリット:自社の業務負担が軽減される
- メリット:複数言語対応など専門的なサポートが受けられる
- メリット:最新の制度情報や法改正に対応してもらえる
- デメリット:委託費用がかかる(一般的に1名あたり月3〜5万円程度)
- デメリット:登録支援機関の質によってサービスに差がある
- デメリット:自社と外国人材との距離が生じる可能性がある
| 項目 | 自主支援 | 登録支援機関委託 |
|---|---|---|
| 費用 | 支援実施の人件費のみ | 委託費 月3〜5万円/人 |
| 専門性 | 自社で習得が必要 | 専門機関のノウハウを活用 |
| 業務負担 | 大きい | 小さい |
| 書類作成・届出 | 自社で対応 | 支援関係は代行(一部制限あり) |
| 言語対応 | 自社で確保 | 専門的な対応可能 |
| 外国人との距離 | 直接コミュニケーション | 間接的になる可能性あり |
特定技能1号外国人を5年間雇用すると考えた場合、登録支援機関への委託費用は合計で180〜300万円程度になる可能性があります。複数の外国人を雇用する場合は、自主支援と登録支援機関の活用をコスト面から慎重に検討する必要があるでしょう。
選択のポイント
どちらの支援方法を選ぶかは、以下のポイントを考慮して決めるとよいでしょう:
- 雇用予定人数:多数の外国人を雇用する場合は、自主支援でも効率的な体制を構築できる可能性があります。
- 会社の規模・体制:多言語対応可能な人材や専門知識を持つ人材がすでにいるかどうか。
- コスト:自主支援にかかる人件費と支援機関への委託費用の比較。
- 専門性:特に法的手続きや多言語対応に関する専門性が社内にあるか。
- 長期的視点:今後も継続的に外国人材を雇用する予定があるかどうか。
📝登録支援機関を活用すべき理由
特定技能外国人の支援は専門的な知識や多言語対応が求められるため、特に以下のような場合には登録支援機関の活用がおすすめです。
専門知識の活用
登録支援機関は、入管法や労働法に関する専門知識を持っているため、複雑な手続きや支援業務を適切に行うことができます。特に初めて特定技能外国人を受け入れる企業にとっては、専門家のサポートは大きな安心感につながります。
業務負担の軽減
10項目の義務的支援は、継続的に実施する必要があり、特に複数の外国人を雇用する場合はかなりの業務負担となります。登録支援機関に委託することで、企業は本来の事業に集中することができます。
制度変更への対応
特定技能制度は2019年に始まったばかりの比較的新しい制度であり、今後も制度の変更や改善が予想されます。2025年4月からの各種変更など、最新の情報を常に把握することは容易ではありません。登録支援機関は制度の変更に関する情報を適時収集し、適切に対応することができます。
多言語対応の確保
特定技能外国人への支援では、「外国人が十分理解できる言語」での対応が求められます。登録支援機関は複数の言語に対応できる体制を整えているため、様々な国籍の外国人材を雇用する場合に特に有効です。
コンプライアンスリスクの軽減
特定技能制度は比較的新しい制度であり、法律や運用が頻繁に変更されることがあります。登録支援機関は最新の情報を把握し、法令遵守のサポートを行うことができるため、コンプライアンスリスクを軽減できます。
登録支援機関選びのポイント
登録支援機関を選ぶ際には、以下のポイントに注目することをおすすめします:
- 支援実績と経験:特定技能外国人の支援実績が豊富であることが重要です。
- 対応言語:雇用予定の外国人の母国語に対応できるかどうか。
- サポート体制:24時間対応の相談窓口があるかなど、サポート体制の充実度。
- 料金体系:委託費用の内訳や追加料金の有無を確認しましょう。
- 提携サービス:転職支援や日本語教育など、追加サービスの有無と内容。
- アクセスの良さ:定期的な面談などがあるため、地理的なアクセスも考慮すべきです。
登録支援機関を選択する際は、費用や対応言語、これまでの実績などを比較検討することが重要です。また、登録支援機関であっても、行政書士法上の制限があることに注意が必要です。
📝行政書士法と注意点
登録支援機関が行える業務には、行政書士法上の制限があり、実務上違反行為となっている部分もみられます。法律上の制限を理解して、委託先の登録支援機関がどのような処理手順を踏んでいるか確認しておくことがコンプライアンスの観点からも重要です。
登録支援機関ができること・できないこと
行政書士法第1条の2により、他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類の作成は、行政書士の独占業務とされています。このため、登録支援機関の職員(行政書士でない場合)ができるのは以下の業務のみです:
- できること:申請取次(申請書類を出入国在留管理局に持参して提出する手続き)
- できること:支援計画の実施(10項目の義務的支援の実施)
- できないこと:在留資格申請書類の作成(行政書士の独占業務)
- できないこと:法律で定められた届出書類の作成(行政書士の独占業務)
実務上の行政書士法違反行為
実際の現場では、登録支援機関が在留資格申請書類や届出書類を直接作成しているケースも見られます。これは本来は行政書士法違反となる可能性があります。
特に注意が必要なのは、形式的に申請書類作成自体を無償とし、申請書類の作成と密接関連する他の役務提供を有償とすることで、実質的に書類の作成を有償で行ったと同視できる場合です。このような場合も、刑事罰の対象となる可能性があります。
書類作成と申請取次の区別
登録支援機関の職員が「特定技能」の在留諸申請について申請取次を行うことは認められていますが、申請書類の作成を行うことはできません。申請書類の作成は、行政書士または弁護士に依頼する必要があります。
また、定期届出書についても、特定技能所属機関の役職員が作成する必要があり、登録支援機関(行政書士または弁護士でない場合)が作成することは認められていません。
適切な対応方法
これらの法的制限を踏まえると、以下のような対応が推奨されます:
- 在留資格申請書類の作成は行政書士または弁護士に依頼する
- 登録支援機関と行政書士が連携して支援を行う体制を構築する
- 定期届出書類は特定技能所属機関の職員が作成する
- 書類作成と申請取次を明確に区別して委託する
これらの法的制限を踏まえると、在留資格申請や届出に関する書類作成が必要な場合は、登録支援機関と行政書士(または弁護士)を適切に活用することが重要です。当法人では、登録支援機関との連携も含め、特定技能に関する適切なサポートを提供しております。
📝2025年4月からの制度変更点
2025年4月1日から、特定技能制度における運用ルールが大きく変更されます。特に支援計画や届出に関する変更点について、主なものをご紹介します。
主な変更点
- 定期届出の頻度変更:3か月ごとから年1回(2026年4〜5月に初回提出)に変更
- 届出書類の統一:「受入れ状況」と「支援状況」が一つにまとめられる
- 支援計画の実施困難時の新たな届出:支援計画通りの実施が難しい場合の届出義務が新設
- 登録支援機関の届出義務:支援において特定技能所属機関の基準不適合を把握した場合も含む
- 不正行為の類型追加:支援に関する法令違反や基準不適合の隠蔽目的の行為が追加
- 地方公共団体との連携義務:共生社会の実現のための施策への協力が義務化
協力確認書の提出義務
初めて特定技能外国人を受け入れる場合、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前に、外国人が活動する事業所および住居地の市区町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。すでに特定技能外国人を受け入れている場合でも、2025年4月1日以降の初回申請時に提出が必要です。
オンライン面談要件の緩和
特定技能外国人との定期的な面談について、一定の条件のもとでオンライン実施が認められるようになりました。条件には以下のものがあります:
- 面談対象者の同意を得ること
- 面談を録画し一定期間保管すること
- 年1回以上は対面で面談を行うこと(初回面談は対面が必須)
これにより、地理的な制約がある場合でも定期的なコミュニケーションを柔軟に行えるようになります。
送迎に関する規定の明確化
登録支援機関が自らの車両を利用して送迎する場合、「生活支援サービスなどとの一体運送」であれば道路運送法違反に当たらないことが明確化されました。
特定技能における訪問介護の可能性
2025年4月に、これまで在留資格「介護」とEPA介護福祉士に限定されていた訪問介護業務への特定技能資格での従事が解禁されました。
提出書類の省略ルールの変更
特定技能外国人の在留諸申請において、一定の要件を満たす場合に提出書類を省略できるルールが変更されます。オンライン申請と電子届出を行い、適正な受入れを行うことが見込まれる機関については、登記事項証明書や業務執行に関与する役員の住民票など、10項目の書類を省略することができるようになります。
これらの変更は、特定技能外国人の受入れや支援の質を確保しつつ、受入れ企業や登録支援機関の負担軽減を図るものです。2025年4月からの新制度に向けて、早めの準備と対応が必要となります。
まとめ
特定技能外国人の雇用には、10項目の義務的支援が必須であり、この支援を自社で行うか登録支援機関に委託するかの選択が必要です。支援が必要な理由は、外国人材が日本社会に適応し、安定して就労できる環境を整えるためであり、外国人材を活用する企業にとっても重要な投資といえます。
登録支援機関を活用すれば業務負担が軽減され、専門知識を活かした効率的な支援が可能になりますが、コスト面での検討も重要です。また、登録支援機関に委託する場合でも、行政書士法上の制限があることに注意し、在留資格申請書類や法定届出書類の作成は行政書士に依頼するなど、適切な対応が求められます。
2025年4月からは制度が大幅に変更され、定期届出の頻度変更や地方自治体との連携義務の追加など、特定技能外国人の雇用や支援に関わる企業・機関は、最新の情報を把握して適切に対応することが重要です。特定技能制度は、日本の労働力不足を解消するために16分野まで拡大し、今後さらなる発展が期待されています。当法人では、特定技能に関する各種サポートを提供しておりますので、お困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。