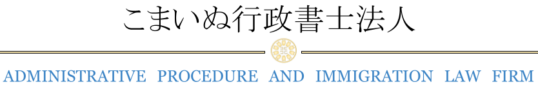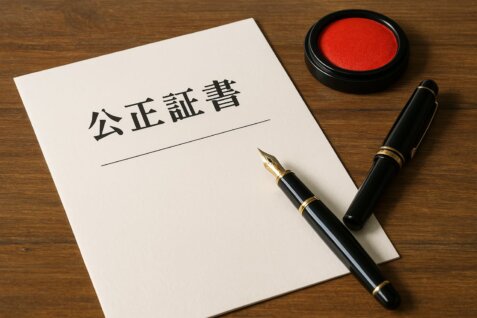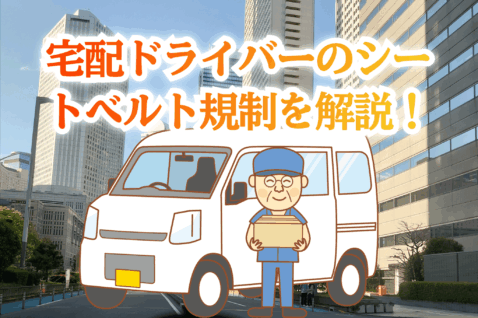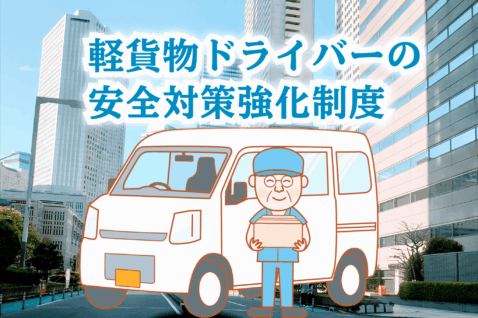知らないと100万円の罰金も?軽貨物運送業の届出と事業用ナンバーの基礎知識

軽貨物運送業を始めたいとお考えの方は、法的な手続きについて正しく理解しておく必要があります。特に「届出制」と「許可制」の違いや、リース車両を使用する場合の手続きなど、重要なポイントがいくつかあります。この記事では、軽貨物運送業の開業に必要な届出や規制について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。これから開業を検討されている方や、すでに業務委託で働いている方にとって役立つ情報をお届けします。
目次
📝貨物運送事業の定義と種類
貨物運送事業とは、貨物自動車運送事業法第2条で「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業」と定義されています。つまり、お金をもらって他人の荷物を自動車で運ぶビジネスすべてが対象となります。
貨物運送事業は、使用する車両の種類や積載量によって以下のように分類されます:
- 一般貨物自動車運送事業:最大積載量が1トン以上の車両を使用する事業
- 特定貨物自動車運送事業:特定の荷主のみと契約して行う運送事業
- 貨物軽自動車運送事業:軽自動車や軽貨物車(最大積載量350kg以下)を使用する事業
- 貨物自動二輪車運送事業:自動二輪車を使用して荷物を運送する事業(ただし125cc以下の原付バイクは対象外)
この分類に基づいて、必要な手続きが「届出制」か「許可制」かが変わってきます。特に軽貨物運送業を始める方にとって、この違いを理解することは非常に重要です。
📝軽貨物・一般貨物・二輪の規制の違い
貨物運送事業を始める際に最も重要な違いは、「届出制」と「許可制」です。これは使用する車両によって大きく異なります。
許可制の対象となる事業
一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業は、貨物自動車運送事業法第3条および第35条に基づき、国土交通大臣の許可が必要です。これらは主に最大積載量1トン以上の車両を使用する事業が対象となります。許可を得るためには、事業計画や資金計画、車両の確保、営業所の設置、運行管理者の選任など、多くの要件を満たす必要があります。
届出制の対象となる事業
貨物軽自動車運送事業(軽貨物)は、貨物自動車運送事業法第36条に基づき、事業開始の30日前までに国土交通大臣への届出で事業を開始できます。この「届出制」という点が、許可制である一般貨物運送事業との大きな違いです。
なお、125cc以下の原付バイクや自転車による配達は、貨物軽自動車運送事業法の規制対象外となっています。そのため、Uber Eatsなどのフードデリバリーサービスで原付バイクや自転車を使用する場合は、貨物軽自動車運送事業の届出は不要です。ただし、126cc以上の自動二輪を使用する場合は届出が必要となります。
| 事業の種類 | 手続き | 根拠法令 |
|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業 | 許可制 | 貨物自動車運送事業法第3条 |
| 特定貨物自動車運送事業 | 許可制 | 貨物自動車運送事業法第35条 |
| 貨物軽自動車運送事業 | 届出制 | 貨物自動車運送事業法第36条 |
| 125cc以下の原付バイク・自転車 | 規制対象外 | – |
届出制は許可制と比較して手続きが簡易になっていますが、だからといって規制がないわけではありません。無届出で事業を行った場合、100万円以下の罰金が科される可能性があります(貨物自動車運送事業法第36条第1項、第75条11号)。また、届出後も安全規則の遵守義務があり、事業者としての責任を果たす必要があります。
📝軽貨物運送業の届出方法
軽貨物運送業(貨物軽自動車運送事業)を始める場合、事業開始の30日前までに国土交通省の地方運輸局に届出を行う必要があります。届出の手順は以下の通りです:
- 「貨物軽自動車運送事業経営届出書」を準備する
- 事業用自動車の数や種類、使用の本拠の位置などを記入
- 車検証のコピーなど、必要書類を添付
- 管轄の運輸支局または運輸局に提出
届出書には以下の内容を記載する必要があります:
- 氏名または名称、住所
- 事業用自動車の数および種類
- 事業用自動車の使用の本拠の位置(営業所の住所)
- 運送の範囲(例:東京都内全域など)
- 事業開始予定日
特に重要なのは「車両情報」です。届出の際には使用する車両の情報(車検証の内容)が必要になります。これは次のセクションで説明する「事業用ナンバー」の取得と密接に関連しています。
届出書の様式は国土交通省のウェブサイトからダウンロードできます。また、当法人でも軽貨物運送業の開業支援を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
📝車両のリースと事業用ナンバーについて
軽貨物運送業を営む場合、通常の黄色ナンバー(自家用軽自動車のナンバープレート)ではなく、「事業用ナンバー(黒ナンバー)」が必要になります。これは黒地に黄色の文字で表記された営業用であることを示す車両登録であり、法的に必須です。
事業用ナンバー取得の流れ
事業用ナンバーを取得するには、まず軽貨物運送事業の届出を行い、運輸局から「連絡所」というものを受け取る必要があります。その後、この「連絡書」を持って軽自動車検査協会に行き、車両の登録変更(黄色ナンバーから黒ナンバーへの変更)を行います。中古で購入した車両を前所有者から名義変更する場合にも、同じくこの「連絡書」が必要となります。
また前所有者の車両が黒ナンバーであった場合には、前所有者がその譲り渡す車両を自分の軽貨物事業から外した旨の届出をして(廃業または減車)、その連絡書も併せて必要となります。
「連絡書」は運輸局と軽自動車検査協会の間で情報を連携するための書類で、貨物運送事業の届出が受理されたことを証明するものです。これがなければ事業用ナンバーを取得することができません。
リース車両の場合の手続き
リース会社から車両をリースして軽貨物運送業を行う場合、車検証の「所有者」欄はリース会社のままで、「使用者」欄を個人事業主(あなた)の名義に変更する必要があります。この手続きは、軽貨物運送事業の届出と合わせて行う必要があります。
具体的な手順は以下の通りです:
- リース契約を締結する
- リース会社と協力して車検証の「使用者」欄を変更する手続きを行う
- 変更後の車検証を添付して軽貨物運送事業の届出を行う
- 届出受理後、連絡書を取得して事業用ナンバーに変更する
重要なのは、たとえリース車両であっても、実際に運送事業を行うのはあなた(個人事業主)であるため、軽貨物運送事業の届出は必ず行う必要があるということです。リース会社が既に届出を行っているからといって、個人での届出が免除されるわけではありません。この点を理解せずに無届で営業すると、100万円以下の罰金が科される可能性があります。
📝業務委託と各種届出の関係
軽貨物運送業界では「業務委託契約」に基づいて働く方が多くいます。特に、軽貨物運送会社からリース車両を借りて業務を行うケースも一般的です。このような場合の各種届出関係について解説します。
業務委託と運輸局への届出
法的に見ると、他人の需要に応じて有償で貨物を運送する場合たとえ業務委託契約であっても貨物運送事業に該当します。つまり、軽貨物運送会社と業務委託契約を結んでいる場合、アルバイト等の雇用契約ではないため、個人事業主として貨物軽自動車運送事業の届出を行う必要があります。
しかしながら実態として、リース車両を使用する場合、車両の名義が運送会社にあるため、運送会社がすでに事業届出を行っているとして個人での届出を行わないケースが存在します。このような状況はいわゆる名義貸しとして法的に問題がある可能性があります。
すなわち名義貸しの規定は条文上、一般貨物と特定貨物のみを対象としており、軽貨物はその対象とはなっていないため、名義貸し行為によってリース会社(軽貨物会社)側が直接的には罰則の対象にはならないとしても、借りた側は無届け営業として上述のように処罰対象となり得ます(貨物自動車運送事業法第36条第1項、第7511号)。
また、リース会社(軽貨物会社)側も状況によっては無届け営業のほう助罪が成立する可能性も否定できません。
リース車両であっても、使用者名義を変更し、事業者として適切に届出を行うことがCSRの観点からも望ましいでしょう。
税務署への開業届との関係
軽貨物運送業の届出(国土交通省への届出)と、税務署への開業届は別のものです。税務署への開業届は、個人事業主として事業を始めたことを税務署に知らせるためのもので、所得税の申告などに関連します。軽貨物運送業を含め、個人事業を始める場合は、原則として開業日から1か月以内に提出することが望ましいとされています。
| 届出の種類 | 提出先 | 目的 | 提出時期 |
|---|---|---|---|
| 軽貨物運送業の届出 | 国土交通省(地方運輸局) | 貨物運送事業法に基づく義務 | 事業開始の30日前まで |
| 開業届(税務) | 税務署 | 所得税の申告のため | 開業日から1か月以内が望ましい |
適法に事業を行うためには、業務委託形態であっても、自分が個人事業主として貨物運送業を営んでいる場合は、国土交通省への届出と税務署への開業届の両方を適切に行うことが望ましいでしょう。特に国土交通省への届出は法的義務であるため、必ず行う必要があります。
📝一人事業者の安全管理者選任と適性診断
軽貨物運送業を個人事業主として開業する場合、安全管理に関する法的義務も理解しておく必要があります。2025年4月1日以降、新規に軽貨物運送事業を開始する事業者には、安全管理者の選任・届出義務が課せられることになりました。
安全管理者の選任・届出義務
一人事業者の場合、自分自身を「貨物軽自動車安全管理者」として選任し、届け出る必要があります。これは貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づく義務で、軽貨物運送事業の届出後、速やかに選任・届出手続きを行わなければなりません。
- 届出事項:氏名、生年月日、選任年月日、講習修了証番号など
- 提出先:管轄の運輸支局を通じて国土交通大臣へ
講習受講の義務
安全管理者に選任される前に、国土交通大臣の登録を受けた講習実施機関による「貨物軽自動車安全管理者講習」を受講する必要があります。また、選任後は2年ごとに定期講習の受講も義務付けられています。これらの講習では、安全運転管理や関係法令、事故防止対策などについて学びます。
適性診断の受診義務
さらに、以下の場合には適性診断の受診が義務付けられています:
- 65歳以上の高齢運転者である場合(年1回以上)
- 死傷者を生じた事故を引き起こした場合(事故発生後速やかに)
適性診断は自動車事故対策機構(NASVA)などの国土交通大臣の認定を受けた機関で受診することができます。診断結果は自己の運転特性を理解し、安全運転に活かすために活用することが重要です。
これらの安全管理に関する規制は、軽貨物運送業の安全性向上を目的としたものです。違反した場合は行政処分や罰則の対象となる可能性がありますので、新規開業を検討される方は事前に必要な講習を受講し、適切な体制を整えておくことをお勧めします。
まとめ
軽貨物運送業を始める際には、「届出制」であるという特徴を理解し、適切な手続きを行うことが重要です。自分で車両を所有する場合だけでなく、リース車両を使用する場合でも、車検証の「使用者」欄を自分の名義に変更し、個人事業主として国土交通省への届出を行う必要があります。無届出で営業した場合、100万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、125cc以下の原付バイクや自転車を使用した貨物運送業は規制対象外であり、届出は不要です。一方、126cc以上の二輪車を使用する場合は届出が必要です。これらの法的手続きを適切に行い、事業用ナンバー(黒ナンバー)を取得することで、適法に業務を行うことができます。軽貨物運送業の開業は、車両調達から講習の受講、届出まで必要な手続きを丁寧に調べてスケジューリングしていけば難しいことはありません。また、こまいぬ行政書士法人では、軽貨物運送業の開業支援も行っておりますので、お気軽にご相談ください。