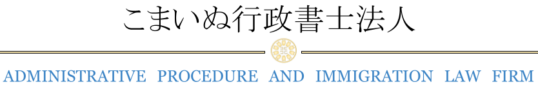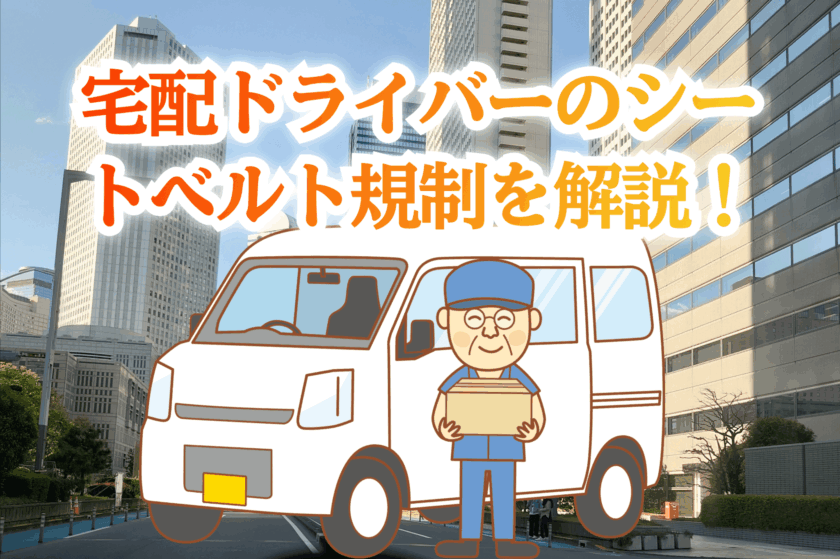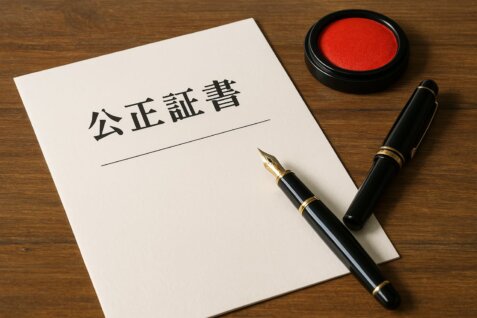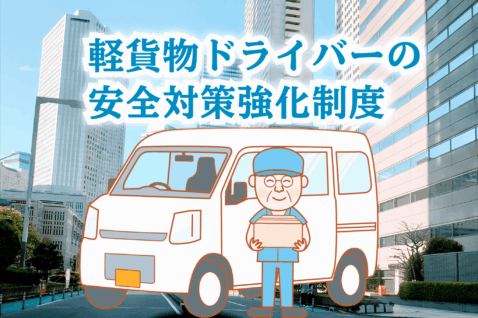知っておきたい宅配ドライバーのシートベルト規制 – 法的根拠と免除条件
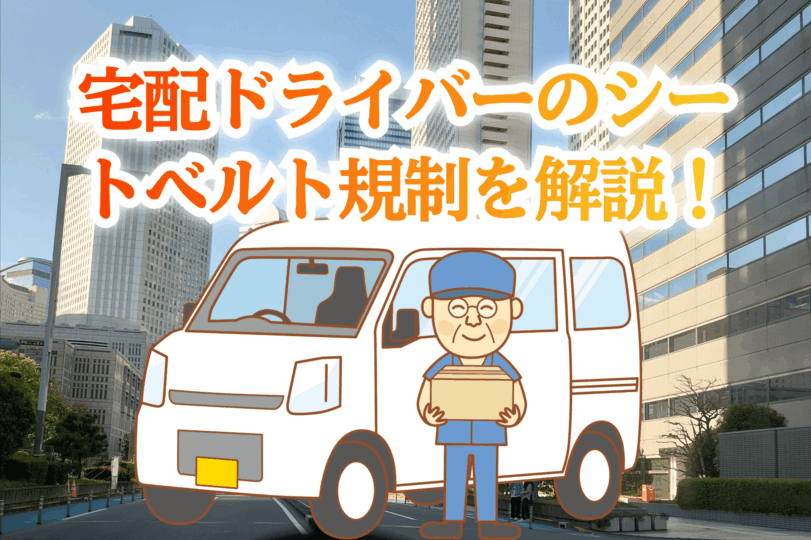
宅配ドライバーのみなさんは、「配達中はシートベルトをしなくていい」と聞いたことがありませんか?実はこの話、完全に正しいわけでも間違いでもないんです。この記事では、宅配ドライバーのシートベルト着用義務について、法律の観点から「どのような場合に免除されるのか」を分かりやすく解説します。配達業務に従事されている方や運送業の経営者の方に、ぜひ知っておいていただきたい内容です。
目次
📝宅配ドライバーのシートベルト着用義務はどうなっているの?
宅配ドライバーのシートベルト着用について、結論からお伝えします。
宅配ドライバーであっても基本的にはシートベルト着用義務があります。ただし、「配達のために頻繁に乗り降りする区間」に限って、例外的に着用が免除されます。つまり、配送センターから配達エリアへの移動など、長距離移動の間はシートベルトを着用しなければなりません。
これは「法律→政令→規則」という3段階の法令構造によって定められています。それぞれどのような内容か、順番に見ていきましょう。
📝道路交通法の基本ルール
まず、シートベルト着用の基本的な義務は道路交通法で定められています。
道路交通法第71条の3第1項(全文)
「(座席ベルト等の装着義務)
第七十一条の三 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」
この条文から分かるように、原則としてすべての運転者はシートベルトを着用しなければなりません。ただし、条文の後半にある「ただし」以降に注目してください。「その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない」という例外規定があります。
では、ここでいう「やむを得ない理由」とは何なのでしょうか?それを知るためには、次の「政令」である道路交通法施行令を見る必要があります。
📝道路交通法施行令による例外規定
道路交通法施行令では、シートベルト着用が免除される「やむを得ない理由」が具体的に列挙されています。宅配ドライバーに関連しそうな部分についてみていきましょう。
道路交通法施行令第26条の3の2第1項第6号(関連部分)
「六 郵便物の集配若しくは取集又はその他の業務で頻繁に自動車の乗降をすることを必要とするもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)に従事する者が、当該業務を行うため自動車を運転するとき(当該業務のうち頻繁に自動車の乗降をすることを必要とする区間において当該自動車を運転する場合に限る。)。」
この条文を噛み砕いて説明すると:
- 郵便配達のような業務、または「頻繁に車の乗り降りが必要な業務」を行う人が
- その業務のために車を運転する場合、シートベルト着用が免除される
- ただし、「頻繁に乗り降りする区間」に限定される
- 対象となる業務は「国家公安委員会規則」で定められている
つまり、ここではまだ宅配ドライバーが明確に対象とされているわけではなく、「国家公安委員会規則で定めるもの」という形で別の規則に委ねられています。では、その規則で何が定められているのでしょうか?
📝国家公安委員会規則による具体的な対象業務
国家公安委員会規則「座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則」で具体的な業務が定められています。
座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則(関連部分)
「二 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定に基づき行う貨物自動車運送事業に係る業務、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十八条第三号の規定による許可を受けて行う貨物の運送に係る業務又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定に基づき行う第二種貨物利用運送事業に係る業務のうち、貨物の集貨又は配達を行う業務
三 米穀、酒類、牛乳若しくは清涼飲料の小売業その他物品の小売業(販売の方法として物品の配達(当該物品に係る容器の回収を含む。以下同じ。)を行うものに限る。)又はクリーニング業に係る業務のうち、戸別に当該物品の配達又は洗たく物の受取若しくは引渡しを行う業務」
この規則のポイントは以下の通りです:
- 第二号:宅配便会社等の「貨物の集貨又は配達を行う業務」が対象
- 第三号:食料品や飲料の配達、クリーニングの集配業務なども対象
上の第二号は、「貨物自動車運送事業」が規定されていて、届出や許可を得て、運送そのものを業務とする事業が当てはまります(いわゆる軽貨物の黒ナンバーや一般貨物の緑ナンバー)。
下の第三号は、上記貨物自動車運送事業に当てはまらず対象外となる「自家用貨物運送」を、この号で拾って対象にしているといえます。余談ですが、例えば酒屋さんの自社商品の配達や、クリーニング屋さんの引取りやお届けなど主要業務の過程として運送が含まれている場合は貨物運送事業ではないといえるので届出や許可が不要です(クリーニング屋さんが黄色ナンバーで集配しているのを見かけたことがあると思います)。
これで、法的な構造が明確になりました。道路交通法で基本的な義務を定め、道路交通法施行令で例外の枠組みを作り、国家公安委員会規則で具体的な対象業務を特定するという仕組みです。
📝「頻繁に乗り降りする区間」とは具体的にどこ?
ここまでの説明で、宅配ドライバーは「頻繁に乗り降りする区間」においてのみシートベルト着用が免除されることが分かりました。では、この「頻繁に乗り降りする区間」とは、具体的にはどのような区間なのでしょうか?
法律上の定義は?
実は、「頻繁に乗り降りする区間」の具体的な定義(距離や回数など)は法令上明確に規定されていません。筆者が調査した限りでは、この点に直接関係する判例も見当たりませんでした。
行政解釈から見る「頻繁な乗降」
国家公安委員会規則の制定趣旨に関連する資料(警察庁通知(昭和60年8月5日)、栃木県警本部長通達(栃交企第4号))等によれば、例えばゴミ収集業務では「道路の路側等において積込、乗車、車両の移動、下車、積込の動作を反復し、従事者の乗降が頻繁であり、移動区間も30メートルから60メートル程度と短い」ことが考慮されていると説明されています。
この解釈を宅配業務に当てはめると、宅配便の配達区間の場合、次のような区分けが考えられます:
- 〇 免除対象:住宅密集地で家から家へ短距離(数十メートル程から長くても60メートル程度)で頻繁に移動しながら配達する区間
- × 免除対象外:配送センターから配達エリアへの移動
- × 免除対象外:配達エリア内でも、次の配達先まで比較的長距離(数百メートル以上)移動する区間
- × 免除対象外:配達終了後の帰路
つまり、単に「宅配ドライバーだからシートベルト不要」ということではなく、業務の中でも「短距離で頻繁に乗降する特定の区間」に限って免除されるということです。実務上も、警察の現場判断としては、短時間のうちに頻繁な乗降を繰り返す区間か否かが重要な判断基準になっていると考えられます。
まとめ
宅配ドライバーのシートベルト着用義務についてまとめましょう。法律の基本は「シートベルトの着用義務あり」です。ただし、宅配業務中の「頻繁に乗り降りする区間」(短距離で次々と配達する場合など)に限り、例外的に着用が免除されます。配送センターから配達エリアへの移動や、配達先間の長距離移動では着用義務があります。「頻繁に乗り降りする区間」の具体的な定義は法令上明確ではありませんが、行政解釈からは30〜60メートル程度の短距離での頻繁な乗降を想定していると考えられます。この規制は安全面を考慮したものですので、免除規定があるとしても、可能な限りシートベルトを着用することをお勧めします。