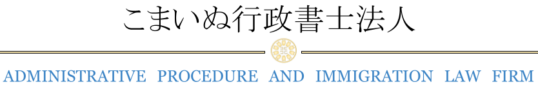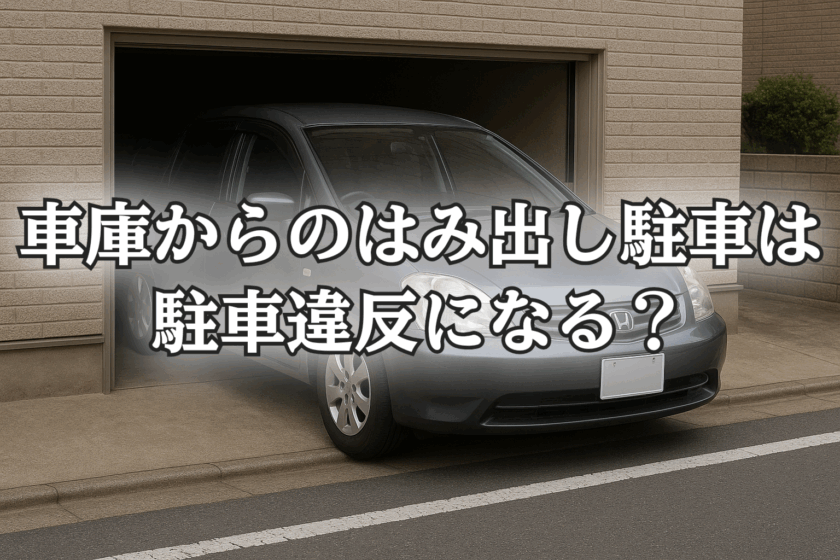車庫からはみ出している車は駐車違反になる?法律の基準と罰則を解説
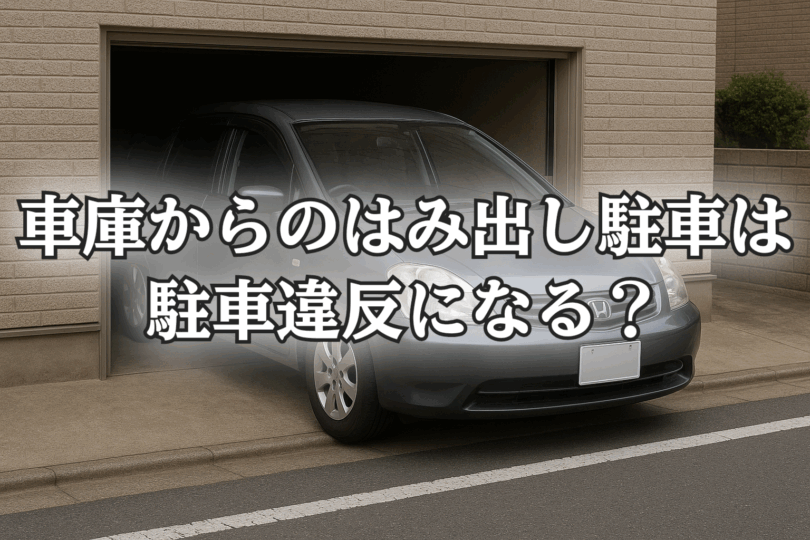
自宅の駐車場に車を停めているのに、車が道路にはみ出していませんか?「少しくらいなら大丈夫だろう」と思っていても、それが駐車違反になる可能性があることをご存じでしょうか。
本記事では、自宅車庫からの「はみ出し駐車」が違反になるのかという疑問について、道路交通法と車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の両面から詳しく解説します。法律の専門用語もわかりやすく説明しますので、安心してお読みください。
📝駐車違反の基本 – 道路交通法と車庫法の規制
はみ出し駐車の話に入る前に、まず駐車違反に関する基本的な法律の枠組みを理解しておきましょう。駐車違反には主に2つの法律が関係しています。
道路交通法による規制
道路交通法は、道路上での車両の通行や駐停車に関するルールを定めた法律です。この法律では、駐停車が禁止される場所が細かく規定されています(道路交通法第44条、第45条)。
たとえば、交差点とその端から5メートル以内、横断歩道の前後5メートル以内、駐車場の出入口から3メートル以内などは、標識がなくても駐車が禁止されています。また、道路標識や道路標示によって駐車が禁止されている場所もあります。
ここでいう「駐車」とは、車両が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(5分を超えない貨物の積卸しや人の乗降は除く)、または車両が停止し、かつ運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいいます(道路交通法第2条第1項第18号)。
車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)による規制
車庫法は、道路を自動車の保管場所(車庫代わり)として使用することを禁止する法律です。正式名称は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」といいます。
この法律の第11条第1項では「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない」と明確に規定しています。また、同条第2項では、自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車すること(夜間は8時間以上)となるような行為も禁止されています。
つまり、道路交通法が「一時的な駐車のルール」を定めているのに対し、車庫法は「道路を車庫として使うこと自体」を禁止しているという違いがあります。
📝はみ出し駐車とは?法的な定義と基準
それでは、本題の「はみ出し駐車」について詳しく見ていきましょう。自宅の駐車場から車体の一部が道路にはみ出している状態は、法律上どのように扱われるのでしょうか。
「道路」の定義を理解する
まず重要なのが「道路」とは何かという点です。道路交通法第2条第1項第1号では、道路を次のように定義しています。
- 道路法に規定する道路(国道、都道府県道、市町村道など)
- 道路運送法に規定する自動車道
- 一般交通の用に供するその他の場所
つまり、公道だけでなく、一般の人が自由に通行できる私道も「道路」に含まれます。自宅前の道路が私道であっても、一般の通行に使われていれば道路交通法の対象となる可能性があります。
車体の一部がはみ出していたら違反になるのか
ここが最も気になる点でしょう。実は、はみ出し駐車が違反となるかどうかは、はみ出した先の道路がどのような場所かによって変わってきます。
駐車禁止場所・駐停車禁止場所へのはみ出し
車体の一部が駐車禁止場所や駐停車禁止場所にはみ出している場合、違反に該当する可能性が高いと考えられます。
駐停車禁止場所の例(道路交通法第44条):
- 交差点とその端から5メートル以内
- 横断歩道とその端から前後5メートル以内
- 道路標識・標示により駐停車が禁止されている場所
駐車禁止場所の例(道路交通法第45条):
- 駐車場や車庫などの出入口から3メートル以内
- 道路標識・標示により駐車が禁止されている場所
これらの場所に車体の一部でもはみ出していれば、駐停車禁止違反または駐車禁止違反に該当すると解釈される可能性があります。
特に規制のない道路へのはみ出し
一方、はみ出した先が駐車禁止でも駐停車禁止でもない、特に規制のない道路部分の場合は、状況が少し複雑になります。
道路交通法第47条では、車両は道路の左側端に沿って駐車しなければならないと規定されていますが、自宅敷地から一部がはみ出しているだけの状態が直ちにこの規定違反となるかどうかは、個別の状況によって判断が分かれる可能性があります。
ただし、以下のような場合は、他の規定に抵触する可能性があります。
- はみ出した部分により、他の車両の通行が妨げられている場合
- 駐車した車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がなくなる場合(道路交通法第45条第2項)
- 歩道にはみ出している場合
車庫法の観点からの問題
道路交通法とは別に、車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の観点からも注意が必要です。
車庫法第11条第1項は「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない」と規定しています。自宅車庫に車を保管しているつもりでも、車体の一部が道路にはみ出した状態で継続的に駐車している場合、道路の一部を保管場所として使用しているとみなされる可能性があります。
さらに、車庫法第11条第2項第1号では、自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為も禁止されています。はみ出した状態で長時間駐車を続けることは、この規定に抵触する可能性があります。
「はみ出し」の程度による違いはあるのか
法律上、「10センチならセーフ、30センチならアウト」といった明確な数値基準は定められていません。
ただし、はみ出しの程度が大きいほど、他の交通への影響も大きくなり、違反として問題視される可能性は高まると考えられます。逆に、はみ出しがわずかで交通への影響がほとんどない場合でも、はみ出した先が駐車禁止場所等であれば違反要件を満たす可能性があります。
実際の取締りがどのように行われているかについては、次のセクションで詳しく説明します。
📝実際の取締りと判断基準
前のセクションで、はみ出し駐車が違反となるかどうかは状況によって異なることを説明しました。では、実際に警察による取締りはどのように行われているのでしょうか。
取締りの実態について
警察には限られた人員と時間がありますので、すべての駐車違反を常時取り締まることは現実的ではありません。実際の取締りでは、交通の安全と円滑を確保するという法律の目的に照らして、優先順位が判断されています。
特に、はみ出した先が明確な駐車禁止場所や駐停車禁止場所でない場合、取締りの対象となるかどうかは、周辺の交通状況や影響の程度などが総合的に考慮される傾向にあります。
取締りの対象となりやすいケース
以下のような場合は、取締りの対象となる可能性が高くなります。
- はみ出した先が駐車禁止場所または駐停車禁止場所である場合
- 道路へのはみ出しが大きく、他の車両の通行を明らかに妨げている場合
- 道路幅が狭い場所で、はみ出しによって交通に支障が生じている場合
- 近隣住民や通行者からの苦情や通報があった場合
- 過去に警告を受けたにもかかわらず、継続してはみ出し駐車をしている場合
- 歩道にはみ出していて、歩行者の通行を妨げている場合
取締りの優先度が比較的低いと思われるケース
一方で、以下のような場合は、すぐに取締りの対象となる可能性は相対的に低いと考えられます。ただし、これは「違反ではない」という意味ではありません。
- はみ出した先が特に規制のない道路部分で、はみ出しもわずかであり、道路幅も十分にあって交通への影響がほとんどない場合
- 住宅街の私道で、交通量が少なく、近隣からの苦情もない場合
ただし、これらはあくまで一般的な傾向であり、取締りを受けないという保証にはなりません。また、車庫法の観点からは、継続的なはみ出し駐車は問題視される可能性があります。
通報や苦情があった場合の対応
近隣住民や通行者から警察に通報や苦情があった場合、警察は現場を確認し、違反が認められれば取締りを行います。通報があった場合は、はみ出しの程度が小さくても対応される可能性が高くなります。
警察から注意や警告を受けた場合は、速やかに改善することが重要です。警告を無視して継続すると、本格的な取締りの対象となる可能性が高まります。
道路状況による判断
同じ程度のはみ出しでも、道路の状況によって判断が異なる場合があります。
- 道路幅が広く交通量も少ない場合:比較的寛容に判断される傾向
- 道路幅が狭く交通量が多い場合:厳しく判断される傾向
- スクールゾーンや通学路の場合:安全面から厳しく判断される傾向
継続性と常習性の問題
一時的なはみ出しと、継続的に車庫代わりとして道路を使用していることでは、意味合いが大きく異なります。
車庫法違反の観点からは、継続的に道路上にはみ出した状態で車を保管していることが特に問題となります。自宅車庫からのはみ出しを常態化させることは避けるべきです。
📝違反した場合の罰則 – 反則金と違反点数
では、実際に取締りを受けた場合、どのような罰則があるのでしょうか。道路交通法違反と車庫法違反では、罰則の内容が異なります。
道路交通法違反の場合
道路交通法違反として取締りを受けた場合、違反の種類によって反則金と違反点数が異なります。
駐停車違反(道路交通法第44条違反)の場合:
- 普通車:反則金10,000円、違反点数1点(道路交通法第119条の3、道路交通法施行令別表)
- 大型車:反則金12,000円、違反点数1点
放置駐車違反の場合:
- 普通車:放置違反金15,000円、違反点数2点(運転者が特定された場合)
- 大型車:放置違反金21,000円、違反点数2点(運転者が特定された場合)
放置駐車違反とは、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態での駐車違反のことです(道路交通法第51条の4)。
車庫法違反の場合
車庫法違反の場合、反則金制度はなく、刑事罰の対象となります。
- 道路を保管場所として使用した場合:20万円以下の罰金(自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条第2号)
- 道路上の同一場所に12時間以上(夜間は8時間以上)駐車させた場合:20万円以下の罰金(同法第11条第2項、第17条第2号)
車庫法違反は、道路交通法違反よりも重い扱いとなっており、前科がつく可能性があります。
運転者責任と使用者(管理者)責任の違い
道路交通法では、平成18年の法改正により、放置駐車違反について使用者責任が導入されました。これは非常に重要なポイントです。
運転者責任:
運転者が警察署に出頭し、交通反則切符(青切符)の処理を受けた場合、運転者本人が反則金を納付し、違反点数が加算されます。
使用者(管理者)責任:
運転者が出頭せず、運転者の特定ができない場合、車両の使用者(通常は車検証に記載されている所有者や使用者)に放置違反金の納付が命じられます(道路交通法第51条の4)。この場合、違反点数は加算されません。
使用者には弁明通知書が送付され、弁明の機会が与えられます。正当な理由がない場合は、放置違反金納付命令書が送付されます。
弁明通知書と放置違反金の仕組み
放置車両確認標章(黄色いステッカー)を貼られた後、運転者が出頭しない場合の流れは以下のとおりです。
- 公安委員会から車両の使用者に「弁明通知書」と「仮納付書」が送付される
- 使用者は弁明するか、仮納付(任意)するかを選択できる
- 弁明も仮納付もしない場合、または弁明が認められない場合、放置違反金納付命令書が送付される
- 納付命令書に従って放置違反金を納付する(この場合、違反点数は加算されない)
このため、「警察に出頭しなければ点数が引かれない」という状況が生じますが、これは制度の想定内の結果です。ただし、放置違反金の納付義務は発生しますし、納付しない場合は督促や車検拒否などのペナルティがあります。
放置違反金を納付しない場合のリスク
放置違反金を納付しないまま放置すると、以下のような措置がとられます。
- 延滞金の発生(納期限の翌日から年14.5%)
- 督促状の送付
- 車検時に車検証の返付が受けられない(車検拒否制度)
- 財産の差し押さえなどの強制徴収
- 繰り返し違反した場合、車両の使用制限命令
📝異議申立制度と対応方法
違反を指摘された場合や放置違反金の納付命令を受けた場合、納得できないときはどうすればよいのでしょうか。
弁明通知書に対する弁明
放置違反金の納付命令を受ける前に、弁明通知書が送付されます。この段階で、事実に誤りがある場合や正当な理由がある場合は、弁明書を提出することができます(道路交通法第51条の4第6項)。
弁明が認められる可能性があるケース:
- 事実誤認等により違反が成立していない場合
- 違反日時において、弁明者が車両の使用者でなかった場合(既に車両を売却していた場合など)
- 違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど、使用者の責に帰すことが著しく相当性を欠くことが明らかな場合
ただし、「少しの時間だった」「トイレに行っただけ」「すぐ戻るつもりだった」といった理由は、通常は弁明として認められません。
弁明書の提出方法
弁明書は、弁明通知書に記載された提出期限までに、書面で提出する必要があります。口頭や電話での弁明は受け付けられません。
弁明書には、弁明の理由を具体的に記載し、それを裏付ける証拠があれば添付します。公安委員会が審査を行い、弁明が認められない場合は放置違反金納付命令書が送付されます。なお、弁明の審査結果について個別の回答は通常行われません。
行政処分に対する不服申立
免許停止や免許取消などの行政処分を受けた場合で、その処分に納得できない場合は、公安委員会に対して審査請求(不服申立)をすることができます(行政不服審査法)。
審査請求の期限は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。ただし、審査請求をしても、処分の効力は停止されません。
交通反則通告制度での対応
交通反則切符を切られた場合、反則金を納付すれば刑事処分を免れることができます(交通反則通告制度)。ただし、納付しない場合は、通告を受け、それでも納付しない場合は刑事手続に移行する可能性があります。
違反の事実に誤りがある場合は、反則金の納付を拒否し、刑事手続で争うことも理論的には可能ですが、実際には相当な労力と時間がかかります。
予防のためにできること
何よりも大切なのは、違反をしないことです。以下の点に注意しましょう。
- 駐車場の大きさを確認し、車両が道路にはみ出さないようにする
- 車庫のサイズに合った車両を選ぶ
- 駐車の際は、必ず車両全体が敷地内に収まっていることを確認する
- はみ出した先が駐車禁止場所や駐停車禁止場所でないか確認する
- 近隣住民から指摘があった場合は、速やかに改善する
- 警察から警告を受けた場合は、必ず対応する
もしスペース的に難しい場合は、車庫の拡張や、別の駐車場の確保を検討することをお勧めします。
まとめ
自宅車庫からの車のはみ出しについて、道路交通法と車庫法の両面から解説しました。
はみ出し駐車が違反となるかどうかは、はみ出した先の道路がどのような場所かによって変わってきます。駐車禁止場所や駐停車禁止場所にはみ出している場合は、違反に該当する可能性が高いと考えられます。一方、特に規制のない道路部分へのはみ出しの場合は、状況によって判断が分かれる可能性があります。
ただし、実際の取締りでは、はみ出しの程度、道路状況、交通への影響などが総合的に判断されます。特に、近隣からの通報があった場合や、継続的に道路を車庫代わりに使用している場合は、取締りの対象となる可能性が高くなります。車庫法違反は刑事罰の対象となり、より重い扱いとなる点にも注意が必要です。
違反を指摘された場合は、放置違反金の納付命令を受ける前の弁明の機会を活用することができます。ただし、正当な理由がない限り、弁明が認められることは難しいのが実情です。
最も重要なのは、違反をしないよう日頃から注意することです。駐車の際は必ず車両全体が敷地内に収まっていることを確認し、安全で適切な車両管理を心がけましょう。